財政分析
| 境港市の財政に弾力性があるかどうか、借金の占める割合が高いか低いか、 財政状況が裕福かどうかなどを判断する4つの指標について解説します。 |
| 15年度 | 89.2% | 12.4% | 17.3% | 0.558 |
| 14年度 | 95.3% | 12.3% | 15.7% | 0.550 |
| 13年度 | 92.2% | 12.7% | 15.7% | 0.540 |
経常収支比率とは、財政構造の弾力性、つまり自由に使えるお金が多いか少ないかを測定する指標です。 人件費や扶助費、公債費など縮減することが容易でない経費(義務的経費)に、市税や地方交付税などの一般財源がどの程度費やされているかを求めたものであり、80%を超える場合は財政構造は弾力性を欠いているとされてきました。地方財政全体が悪化している今日では、大部分の市町村が80%を超えて要注意の状態です。 この比率が100%を超えると、恒常的に必要な経費が収入でまかなえていない状態になっていることを示します。 境港市では、事務事業の見直しや、借入金を低金利で借り替えるなど、この比率が上がるのを抑える努力をしていますが、平成13年度決算から90%を超え非常に厳しい状況にあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
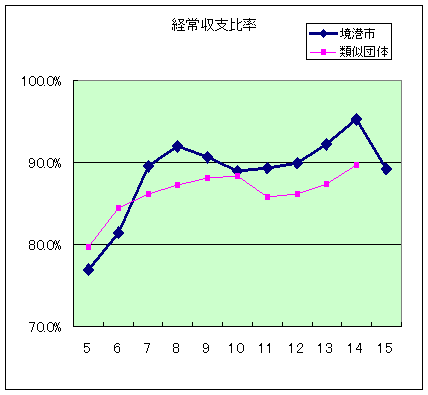 県内四市の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※下記の表でわかるように、歳入で市税、地方交付税が伸び悩む中、歳出では生活保護費や児童措置費などの扶助費、また介護保険会計や下水道事業会計への繰出が増加傾向にあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:%、百万円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※類似団体 全国の市町村を「人口」と「産業構造」を基に類型化したものです。各団体が態様の類似している団体における財政の実態を把握し、それをもっとも身近な尺度として利用することは、自らの財政運営の問題の所在を明らかにし、財政の健全性確保に向けて検討するにあたって有効であると言われています。 |
起債制限比率は、公債費(借金の返済額)の状況から、財政運営の弾力性を測定する指標です。 現行の地方財政制度では、公債費の一部が地方交付税によってまかなわれる仕組みになっています。公債費負担比率は、この影響を考慮しないのに対し、起債制限比率はこの影響を考慮する指標となっているので、自力で(すなわち地方交付税以外の財源で)公債費を償還する度合いを見るための指標となっています。 このため、この指標は、地方債(市債)の発行を許可するときの基準となり、20%以上になると、財政の健全化を確保するために、地方債の許可について一定の制限を受け、さらに30%以上になるとほとんどの地方債が許可されなくなります。 境港市では、平成8年度に警戒ラインの15%超えたことをうけ公債費負担適正化計画を策定し、計画に基づき財政構造の健全化に努めています。 しかし、平成12年度の鳥取県西部地震、平成13〜14年度の清掃センター改造事業(ダイオキシン対策)に多額の市債を借り入れましたので、今後これらの償還が本格化してきます。平年ベースでは市債借入の抑制に努める必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
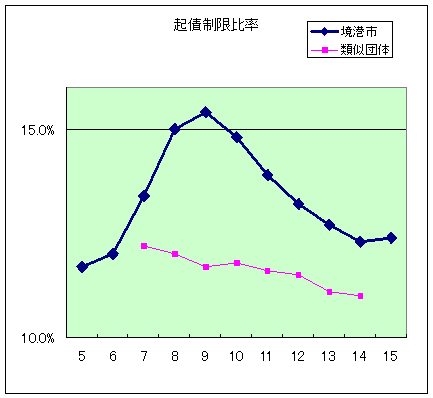 県内四市の状況
|
財政力指数は、財政運営の自主性の大きさを表す指数です。1に近いほど財政力が強いことを表しています。 財政運営をするのに必要となる一般財源のうち、自前で調達できる市税がどのくらい確保できるかという割合を理論的に求めたもので、1を下回れば、自主財源(市税など)だけでは財政運営ができない状態であり、地方交付税が交付されます。逆に、1以上になると、自立して自主的に財政運営ができることになるので、地方交付税が交付されない、いわゆる「不交付団体」となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
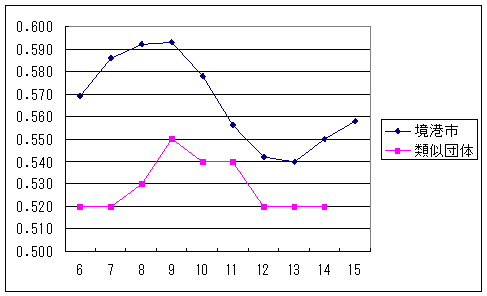 県内四市の状況
|