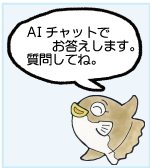第2回境港市みんなでまちづくり推進会議(平成23年4月27日開催)
第2回境港市みんなでまちづくり推進会議会議録
日時:平成23年4月27日(水) 18:30~20:15
場所:境港市中央公民館
日 程
1.開会
2.平成23年度境港市市民活動推進補助金の審査
3.その他
4.閉会
出席者(敬称略)
石橋文夫 梶川恵美子 黒見久司 土井哲雄
三島智子 渡部敏樹 角徹 植田建造
(欠席委員:赤石有平 柏木好輝 波田純子)
<開会>
(地域振興課長)
4月の人事異動で、前任田辺課長から柏木が後任で課長になりました。そして私の後任が北野です。盛山は代わっておりませんので、よろしくお願いします。
今日はご出席いただき、誠にありがとうございます。いつも貴重なご意見や熱心なご議論をいただき、感謝申し上げます。
今日は市民活動推進補助金の審査ですが、今回から要綱を一部改正し、活動や経費など、補助対象の範囲を広げています。この要綱の改正について、今年1月の第1回みんなでまちづくり推進会議の中で、皆さんにご意見をいただきました。その中で一部取り入れられないものもありましたが、今後、取り入れられるものは検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(黒見会長)
今回の審査員は、石橋さん、角さん、土井さんにお願いしております。
(事務局)
それでは今日の会議の進め方及び審査の視点について説明します。
本日プレゼンテーションを3団体に行っていただきます。
1団体15分です。まず、最初の3分で申請概要の説明をしてもらい、残りの12分間で審査員に説明をしていただきます。その間審査員以外の方には傍聴をしていただきます。
それでは今日の会議の進め方及び審査の視点について説明します。
本日プレゼンテーションを3団体に行っていただきます。
1団体15分です。まず、最初の3分で申請概要の説明をしてもらい、残りの12分間で審査員に説明をしていただきます。その間審査員以外の方には傍聴をしていただきます。
プレゼン終了後19時45分から皆さんで討議をします。そこで審査表などを参考にしながら1件ずつ採択・不採択・修正の確認及び決定をしていただきます。
継続分の緑化事業は、書類審査のみです。緑化事業については、市としては基本的に認めたいという考えをもっております。
また、今年度から境港市市民活動推進補助金交付要綱が一部改定となりました。対象が、「一過性のイベント等を開催するために組織された団体(実行委員会)」や「現に活動している市民活動団体が新たに取り組む事業又は活動を拡充するための事業」も補助の対象としますので、よろしくお願いします。
(渡部委員)
その3件については、要綱から逸脱しているなど、大きな問題点はありませんね。
(黒見会長)
基本的には、補助金の予算を削るというよりは、補助金を活用しながら、しっかりと活動をし、みんなで一緒になってまちづくりをしていってほしいと思います。
一般事業は、今年度に入ってまだ3団体ですから、補助の対象となるような団体には補助金のPRをしていってほしいと思います。
<申請団体によるプレゼンテーションの開始>
◇1団体目 女声合唱団 沙羅
・申請事業 「女声合唱団沙羅 4th Concert」
・事業内容 舞台内容を普段にも増して充実させることにより、多くの市民の方々に合唱音楽の楽しさを満喫して頂き、今後市内の合唱活動を促進させる。
(石橋委員)
アルバイト料が16名で44,000円となっていますが、ボランティア団体等に依頼をした
ら安価でできる場合もありますので、このようなことも今後考慮に入れていただきたく思います。
(女声合唱団沙羅)
駐車場係はボランティアでもよいかも知れませんが、舞台に関することは、他の合唱団に所属しているなど、舞台のことや楽器の扱いについてある程度分かっている人がいいです。
(石橋委員)
分かりました。
それともう1点ですが、チケットの販売が200枚となっていますが、もしチケットが200枚売れなかった場合は、どのようにされますか。
(女声合唱団沙羅)
積み立てをするなど、自己負担をします。
(角委員)
東京からの旅費とありますが、これはどういうことでしょうか。
(女声合唱団沙羅)
尺八の先生を東京からお招きしています。
(角委員)
指揮者はどちらの方ですか。
(女声合唱団沙羅)
松江の方です。
(角委員)
今回補助が出なかった場合は自己負担で活動を行うとのことですが、経費面も含めて、他の合唱団がどのように活動をしているかなど、情報交換等の交流はされていますか。
(女声合唱団沙羅)
イベントなどで交流をしたり、お互いの演奏会を聴きに行ったり、また、一緒に参加したイベントの反省会などで、各々の活動内容や問題点などの情報交換をすることはあります。しかし、運営のことについてはあまり話をしたことはありません。するとしたら、会費程度です。
(土井委員)
申請内容はよいと思います。高校生以下は無料というのもよいと思います。ただ、文化ホールには200人以上のお客さんが入れるので、チラシのみの広報ではなく、PTAの方からも宣伝してもらうようにするなどすると聴きにくる子どもが増えると思います。
(女声合唱団沙羅)
以前境高と交流したことがありますが、日曜日の外部団体のイベントに関して、学校を通して要請等をすることは、難しいので、学校外の少年少女合唱団を通しての広報ということになります。
高校生以下は無料にしないとなかなか来てもらえません。今の子ども達は吹奏楽中心なので、寂しく思います。
(地域振興課長)
境港市には、このような合唱団が他にもありますか。
(女声合唱団沙羅)
あります。
(地域振興課長)
他の団体にも補助金を使ってもらって、活動を活発にしてもらいたいので、PRをしていただけたらと思います。
◇2団体目 手織工房藍慈彩
・申請事業 「機織り再興プロジェクト手織工房「藍慈彩」」
・事業内容
今年の11月18日~11月20日の3日間、市民会館の展示室にて、手織工房藍慈彩の作品展を行う(朝10時~夕方4時まで)。コーナーも設置し、機織り体験をしていただく。
(角委員)
弓浜がすり伝承館と手織工房藍慈彩さんとは、別のものですか。
(手織工房藍慈彩)
伝統を守った純粋な弓浜絣をしておられるところもありますが、私達は日常生活に使え
るものを作っていくようにしています。
(石橋委員)
子どものためのおくるみを作る、高齢者のためにひざ掛けを作るなど、作ることの目的
があって、よいと思います。
ただ、アルバイト料1,000円×5人×3日とありますが、ボランティア団体の人を雇えば、
もっと経費を削減することができると思いますので、このことも考慮に入れてほしいと思
います。
(手織工房藍慈彩)
多少の弓浜絣に関する技術がある人でないと難しいです。
(角委員)
事業費内訳の展示作品の材料費75,060円とありますが、これはどういったことに使うの
ですか。
(手織工房藍慈彩)
糸代です。
(地域振興課長)
事業は3日間の計画ですが、事業終了後に例えば1週間に1度、機織体験ができるとい
う試みなどは考えてはおられませんか。
(手織工房藍慈彩)
昨年度、機織教室を実施しておりますが、10名募集したところ40名の応募があり、今待
っている人がいる状態です。その人達対象の教室が終わった後で、また何らかの形で募集をかけるか、ボランティアセンターでやっている手づくり市で、一般に体験できるようなコーナーを開設することも考えております。
(地域振興課長)
機織をより市民に広げていくために、作品展以後もされてはどうかと思いますが、待っている人がたくさんおられるようでは、難しそうですね。
◇3団体目 西森岡とんど囃子保存会
・申請事業 「とんど囃子保存事業」
・事業内容
毎月1回、とんどさん1ヶ月前より毎週1回西森岡会館で、指導者も含めて12名で練習をする。とんどさんの練習
をする。
をする。
(土井委員)
今回は横笛10本を購入し、最終的には、自分達で製作するということですね。
(西森岡とんど囃子保存会)
横笛を購入することのみの申請です。購入ができたら、あとは町内会からも応援がもらえると思います。ただ、横笛がそろわないとみんなもその気になりませんので、今回申請しました。
(土井委員)
分かりました。
(石橋委員)
市の補助金をもらって行う事業ですので、とんどさんだけにとどまらず、子どもみこしやみなと祭などに出るなど、今後市内のほかの地域の人に見てもらえるようにしたらいいと思います。
子どもや若者を巻きこんで、地域の伝統を残していってほしいと思います。
(角委員)
石橋委員の発言にもありましたが、1年のみで終わらせず、祭などの行事に参加したら、より地域に密着できますし、もっと発展すると思います。
今後も活動の輪を広げるために必要なものに申請に関する申請をしていけばいいと思います。
最近どの地区でも、とんどさん等の行事が、年々寂しくなっているように感じていますので、後継者の育成にも貢献していただきたく思います。
(西森岡とんど囃子保存会)
そうありたいです。
(地域振興課長)
活動が活発になるよう、補助金を使っていただきたく思います。
(西森岡とんど囃子保存会)
みんなに市からの補助金をもらったという意識ができたら、この事業は続くと思います。高齢者ばかり集まるのではなく、若者も参加できるようなものにしていきたいと思います。
楽譜が読める読めない関係なく、音を聞いているうちにリズムが頭に入って、自分達で演奏できるようにしたいと思います。
指導者は、西森岡在住で、境一中の音楽教諭のハマダアツコさんを予定しています。
(石橋委員)
息の長い団体活動を続けてください。
<プレゼンテーション終了>
(黒見会長)
これから、総評と採点を行います。
まず最初に「女声合唱団沙羅」について、意見がありましたらお願いします。
(梶川委員)
コンサート会場は400人以上入れるので、PR方法を考え、より多くの住民が参加できるようにしたらよいと思いました。
(渡部委員)
自己負担金がかなり多いですが、このお金はどこから出てきたのか分かりません。会費なのかも知れませんが、会費のことについても明記されていません。
あと、収入の自己負担金は324,676円ですが、支出のその他の経費は352,000円となっています。しかし352,000円が自己負担金となるべきで、差額がチケットを売ったお金から補填されるのは、おかしいと思います。自己負担金とは別に事業収入だけでは補助対象経費をまかなえないから補助金を申請するというのが、本来の筋だと思います。
(土井委員)
そこまで細かくみる必要はないように思います。あくまでも予算書では自己負担金は324,676円で、事業費内訳のその他の経費が352,000円というだけのことだと思います。
(渡部委員)
いえ、事業資金だけでは足りないから、補助金を申請するのであって、補助対象経費分の満額をもらおうという考え方は、おかしいと思います。
(黒見会長)
要綱の条件は満たされているが、金銭的に余裕があり、市から補助金をもらわなくてもやっていけるような印象を受けました。
あと、梶川委員の発言にもありましたが、住民参加度が低いように思います。
(三島委員)
皆さんがおっしゃるように、あまりにも裕福であるという印象を受けました。もう少し経費を切り詰めることができると思います。
(黒見会長)
経費や住民参加度で少し疑問があります。今後は事業収支計画について市からも指導をしてほしいと思います。
(植田委員)
毎月会費を払っており、そこから先生への月謝や楽譜代などに充てていると思います。
あと、チケットですが、300枚は売れると思います。最低で200人を見越しているということではないでしょうか。
(黒見会長)
報告書のチェックは市がされますので、決算の段階で実際の入場料を申告してもらって、事業収入が20万円を超えた場合は、その分の補助金は返還するべきです。
それでは、要綱の条件に合っているものは通すのが基本筋ですので、通したいと思いますが、次回の申請時には、市からも申請団体に収支計画面等でいろいろと指導してください。
<採択>
(黒見会長)
それでは、次は手織工房藍慈彩の審査に移ります。
(三島委員)
団体さんも前向きですし、今後途絶えさせたくない活動です。
(石橋委員)
地域の伝統を重んじることはいいことですから、一過性のもので終わらせず、今後も後継者育成に努めてもらいたいです。
(黒見会長)
収支事業計画書の講師への謝金と交通費についてですが、講師というのは、手織工房藍慈彩以外の会員以外の方ですよね。
(三島委員)
おられるそうです。
(渡部委員)
弓浜がすり伝承館とは運営方針も異なるので、講師も弓浜がすり伝承館とは、別のところから呼んでおられますね。
(黒見会長)
弓浜がすり伝承館のような伝統工芸とは違って、日常品を作るという方針ですからね。
それでは、手織工房藍慈彩も異議なしということでよろしいですね。
<採択>
(黒見会長)
それでは、西森岡とんど囃子保存会の審議に移ります。
梶川委員から、お願いします。
(梶川委員)
地域的なことですし、いいと思います。
(石橋委員)
とんどさんだけで終わらせず、地域のお祭やコンサートなどで発表したらいいと思います。
(梶川委員)
それを見た市内の他の地区の人達も誘発されて、広がっていくと思います。
(石橋委員)
囃子にしても神楽にしても、次に続けていくことが大切です。
(梶川委員)
伝統文化的なものは、三世代交流にもなるので、いいと思います。
(渡部委員)
伝統文化の継承が、広がっていくといいと思います。
(石橋委員)
そうすると地域がまとまっていきます。
(黒見会長)
発表の場があると、子ども達もやる気がでます。
それでは、内容等おおむね良好ということで、採択とします。
<採択>
<緑化継続7団体 採択>
(黒見会長)
その他何かありましたら、お願いいたします。
(石橋委員)
昨日の境地区の市長と語る会で、市の町内会の助成が一世帯あたり700円から900円に上がったと聞きました。これは、いいことだと思います。各自治会は最初のコミュニティですから、これが発展しない限りは、市も良くなりません。中には何でも市にやらせればいいという人もいますが、みんながやって協働のまちづくりになると思うので、各自治会とも発展していって、自発的に活動していけたらいいと思いました。
もう1点、町内の吸収合併(区割り)についてですが、このことについては各自治会にまかせきりでなく、市と自治会が一緒になって取り組むべきだと思います。そうしないといつまでたっても問題が置き去りになったままです。
(梶川委員)
何年もこの話は出ていますが、いつまでたっても堂々巡りです。自治会が分裂しているのには意味があるので、難しいです。
(黒見会長)
今の話は境地区の話ですが、境地区全体で集まった時に自治会の合併の話を出すのは、タブーなのですか。
(植田委員)
境公民館での会でその話も出していますが、小さい自治会は、その会自体にも来ません。京町だけで5つもの自治会がありますが、9件だけの自治会もあります。
(黒見会長)
そういったところを統合することはできないのですか。
(梶川委員)
そういったところを統合することが、難しいです。
(植田委員)
運動会は一緒のチームで出ますが、活動は別々です。
(黒見会長)
この話は、行政からも出てきませんよね。
(植田委員)
以前、町内会長さんの方から市の方で自治会の合併を進めるように頼んだようですが、自治会長さん達で集まって話し合いを進めるように言われたそうです。
(黒見会長)
行政が言っても、無理だと思います。
(石橋委員)
でも、自治会の合併に取り組んでいかないといけない時期にきたと思います。
(黒見会長)
外江や渡なども区の合併の問題もあるんですね。
(土井委員)
中野に関しては、小学校区が上道と余子に分かれているので、公民館活動が非常にややこしいです。
(地域振興課長)
世帯数の減少もあり、皆さんが自治会の合併について問題意識をもたれていますが、いざ合併となると、今のままの方がやりやすいなどの理由で、賛成ではないようです。
(三島委員)
あと、花町や東本町や上道町など、境界線がごちゃごちゃしています。それが何とかならないものかとも思っています。
(梶川委員)
区画整理の際に、いろいろとあったようですね。
(石橋委員)
この問題は、その時になってからでは遅いです。今取り組むべきだと思います。
(梶川委員)
境地区は、防災地区の単位で合併してはどうかという話もありましたが、結局まとまりませんでした。
(地域振興課長)
是非、皆さんで先進事例を作っていただきたく思います。
(植田会長)
馬場崎町は、明治町や湊町などとグランドゴルフやみぞそうじをしたりしており、仲がいいです。合併はできませんが、防災等の関係では、非常にいいです。
(土井委員)
必要以上の合併はしなくてもいいと思います。ばらつきがなくなれば、それでいいと思います。
(植田委員)
今回は新年の大雪の雪かきで、協力し合ったと思います。その時に町内の人同士、お互いを知ることができたと思います。
(石橋委員)
近所の者同士の顔見せができました。
(梶川委員)
今までは、挨拶もしないこともありましたから。
(黒見会長)
境からいい実例を示しながら、協働のまちづくりが広がっていけばと思います。
<閉会>