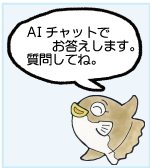第3回境港市みんなでまちづくり推進会議(平成22年5月10日開催)
第3回境港市みんなでまちづくり推進会議会議録
日時:平成22年5月10日(月)18:30~21:00
場所:境港市中央公民館
日 程
1.開会
2.平成22年度境港市市民活動推進補助金の審査
3.その他
4.閉会
□出席者(敬称略)
赤石有平 石橋文夫 梶川恵美子 三島智子
渡部敏樹 角 徹 植田建造
(欠席委員:黒見久司 柏木好輝 土井哲雄 波田純子)
<開会>
(事務局)
市民活動推進補助金の審査を去年2回ほどやっていただきましたが、今年も第1回目をお願いしたいと思います。
地域振興課の方でも異動がありまして、課長が寺澤から田辺に代わりました。担当も渡邉から盛山に代わりました。
それでは今日の会議の進め方等について説明します。今日の審査ですが、審査を推進委員の中から選出する3名と地域振興課長の計4名で行います。推進委員から選出する審査員の3名を、植田さん、石橋さん、梶川さんの3名にお願いしたいと思います。
審査の仕方ですが、1団体の申請の概要は3分でしていただきます。残り12分の間で審査員の皆さんに質疑をしていただきます。審査員以外の方には傍聴をしていただきます。
プレゼン終了後8時から皆さんで討議をします。そこで審査表などを参考にしながら1件ずつ採択・修正の確認及び決定をしていただきたいと思います。
継続分の緑化事業は、書類審査のみです。緑化事業については市の方もどんどんやっていただきたいという立場ですので、基本的には認めたいと思っております。
審査の視点としては、活動の継続性(補助終了後も継続して活動できるのか)、住民の参加度(より多くの住民が参加できるかどうか)、経費(補助がなければできない事業なのか)をみていただけたらと思います。
(赤石副会長)
公共性というのは必要ないのでしょうか。
(事務局)
別紙2の社会貢献性の所で、公共性ということも書いてありますので、みていただきたいと思います。
公共性ということで課題等がありましたら、今後の審査のあり方に取り入れていきたいと思います。
<平成22年度 中海市長事業計画について>(別紙)
<申請団体によるプレゼンテーションの開始>
◇ 1団体目 境港九条の会
・ 申請事業「境港九条の会5周年記念公演」
・ 事業内容
境港市文化ホールにて、コメディアン松元ヒロによるコントを行う。笑いを通して平和の大切さを市民に感じてもらう。
(石橋委員)
憲法というと堅いイメージがあります。しかし今回笑いを取り入れたということで親しみというか、違った感覚で入っていけると思いました。笑いを取り入れて一段下がってみんなと一緒に憲法を語ってもらうことは、いいことだと思います。
(植田委員)
松元ヒロさんといえば、1000人規模で集まるのではないかと思いました。チケット代も安いので市民会館で行ったらいいのではないでしょうか。
(境港九条の会)
境港で1000人集めるのはやはり大変です。収容人数としては境港市文化ホールが一番いいかと思います。
チケット代も本来ならば3~4000円が相場です。しかしそういうわけにはいかないので、補助金でその分を賄いチケット代を安くしました。多くの人に参加してもらい、会場を満員にしたいです。
(梶川委員)
普段の勉強会には、どれくらいの人数が集まられますか。
(境港九条の会)
運営の会を第一金曜日、学習会を第四金曜日にしていますが、学習会には平均10人程度集まります。講師を招く場合、大会議室で行うと80~90人くらい集まります。手前の部屋でやったら、30~40人集まります。
(梶川委員)
もし補助金が出なかった場合には、お金の出所はあるのでしょうか。
(境港九条の会)
寄附と持ち出しです。以前は会費を年1000円いただいていましたが、今は集めていません。全国的にも会費をとっていないところがほとんどです。
◇ 2団体目 京和自治会
・ 申請事業 「京和会花いっぱい運動」
・ 事業内容
京和会20世帯の家の道沿いにプランターを設置する。会員による月1回の花の手入れと植替え等の作業を通して、町内道路沿いの美化を図るとともに、会員の親睦を深める。
(石橋委員)
インターネットで補助金のことを知ったと言っておられましたが、もしそのことを知らなかった場合には、どうされていましたか。
(京和自治会)
予算的に無理なので実施できません。
(梶川委員)
プランターは個人で管理するのですか。
(京和自治会)
一応個人ということにしております。しかし小さい町内でお互いの目がとどきますので、みんなで話し合い等をして管理し、その中で親睦が図れたらと思います。
(植田委員)
シールはいい考えですが、プランターの値段のわりにシールの値段が高すぎると思います。その値段のプランターは2年程で劣化してしまうので、とりあえず今回はマジックなどで手書きにされると自己負担が軽減されると思います。そして次回新たにプランターを購入される際に、2~3年を見越してもう少し高価なものにし、その時にシールを作られたらいいのではないでしょうか。
(梶川委員)
シールが高いのであれば、ラミネートを使うのもきれいだし経済的かと思います。
(京和自治会)
シールが高いというのであれば、シールは両面につけて80枚ですので、片面分の40枚注文するようにしたいです。ぜひシールによって「花いっぱい運動」をアピールしたいと思います。
(植田委員)
プランターのわりに土が少ないのではないでしょうか。その量では1年ももたないと思います。土は定期的に代えないといけませんから。
(京和自治会)
私たちも慣れていないので、いないさんに量や値段の見積もりをしてもらい、そろえてもらうことにしました。作業する場所は近所の空き地でしようとこの前の総会で決まりました。使用許可もとれました。
(石橋委員)
とにかく1年目なのでがんばっていただきたいです。花のない町内はゴミが捨てられていることが多いですが、反対に花のある町内はきれいですから。
取り組みとしては非常にいいことなので、後継者も育成し、ぜひ次の世代にも引き継いでいただきたいです。
◇ 3団体目 あいあい境港
・ 申請事業 「家庭教育力啓発事業」
・ 事業内容
10月上旬、中野町正福寺にて思春期世代の子どもをもつ親の意見交換会を行なう。事例検証・意見交換を通して、参加者同士がつながり、子育ての悩みの解決・ヒントになるようなものにする。
(石橋委員)
講師に誰をよぶかなど、具体的にはどのような取り組みをしますか。
(あいあい境港)
10月の第1か第2金曜日の夜に中野町正福寺の本堂で開催を予定しています。参加者は70名程度を予想しております。事業内容としては、参加者の年代を混ぜて小グループを作り、そこで具体的な事例を挙げ、その事例を基に話し合いをします。それを最終的には全体で発表し、最後に講師の先生に総括していただきます。講師の先生に関しては現在3名ほどに当たっていますが、まだ決定はしていません。
(梶川委員)
チラシを作る際にコピーを70人分されるということですが、コピーを印刷にすることはできませんか。
コピーはお金がかかるので、印刷にした方がよいかと思います。印刷は市民活動センターでもできます。
コピーはお金がかかるので、印刷にした方がよいかと思います。印刷は市民活動センターでもできます。
(あいあい境港)
市民活動センターで印刷すると、だいたい値段はいくらになりますか。
(梶川委員)
1枚2円くらいです。ですからコピーで1枚20円というのはちょっと高いです。補助金で活動するならできるだけ安くあげていただきたいと思います。
(植田委員)
会費はとらずに寄附金で活動しておられますか。
(あいあい境港)
はい。趣旨を話していただきにまわっています。それも広報の一つです。また一般会員4名で参加者をチラシ等で呼びかけています。
(植田委員)
会場整理員さんや幼児託児保育指導員さんには、3000円ずつ支給されるのですよね。
(あいあい境港)
はい。でも去年も小さい子どもが12人来たので、保育指導員さんが二人では足りなくて、大きい子どもにボランティアで手伝ってもらいました。
(植田委員)
ポスターデザイン料が5000円というのは、セミプロさんに頼んだのですか。
(あいあい境港)
はい。しろうとさんでは公共の場所に貼るようなポスターはなかなかできません。
(石橋委員)
昨今少子化と言われておりますが、まだ子育てに関するサービスが充実していないように思います。しかし次世代の子どもたちはしっかりと育てていかなければなりません。ですからこの事業をぜひ継続させていっていただきたいと思っています。
コストを削れるところは削り、みんなでアイディアを出し合ってがんばってください。
(植田委員)
会員さんは増やさないのですか。
(あいあい境港)
賛同してくださる方がいらっしゃったら、入っていただきたいです。
事業もできるだけ継続していきたいと思います。
<プレゼンテーション終了>
(赤石副会長)
では総評に入ります。今日は欠席の黒見会長の代わりに、私が進行を務めさせてさせていただきます。
今日の審査会のやり方としては、委員が発言し他の人は後ろで傍聴していたわけですが、いろいろとやりにくさもあったと思います。今後どのようなやり方で進めていったらいいのかということも含め、意見を出していただきたいと思います。
(石橋委員)
京和会以外は前にも審査を受けたことのある団体ばかりでしたね。
(赤石副会長)
境港九条の会はいかがでしょうか。
(石橋委員)
(赤石副会長)
境港九条の会はいかがでしょうか。
(石橋委員)
私は「憲法9条」をお笑い芸人をよんでやわらかく親しみやすくしたことは、いいことだと思います。
(角委員)
私はもっと堅くしっかりとした内容でもいいと思います。
(赤石副会長)
平和憲法を守ろうとすることに異論はありませんが、思想的な点においては疑問が残ります。「公共性」という審査項目がありますが、この団体に関してはどのように考えていったらいいのかが難しいです。
(事務局)
広く「憲法9条」のことを市民の皆さんに知ってもらうという意味では、公共性は十分あると考えられます。しかし一部の偏った思想が入ってくると、公共性があるとは言えません。ただ県でもそういった事例があったようですが、思想的なものを含むから駄目だとは言えないとのことです。補助対象として平和活動は認めることになっているので、公共的な活動という判断をせざるを得ません。
(赤石副会長)
思想的な面を含むので判断は難しいと思います。しかし憲法9条を広く市民に知ってもらう会を開くということで、昨年も継続事業として採択しました。そのことに関して地域振興課長さん、いかがでしょうか。
(地域振興課長)
平和活動に異論はありません。全市民対象ということで市民活動としても認められます。
(赤石副会長)
それでは採択ということでよろしいでしょうか。
<全員賛成>
(赤石副会長)
境港九条の会の申請は採択いたします。
京和自治会の「京和会花いっぱい運動」についてはいかがでしょうか。
(渡部委員)
花を通じて地域住民の交流を図ることはいいことです。しかし京和自治会は20世帯しかなく運営が大変だと思います。補助金がないと活動できないと思います。
(三島委員)
花いっぱい運動そのものはいいことですが、補助金をもらうからには成果をこちらに分かるようにしていただきたいです。
(角委員)
補助金をもらってやっている事業ですから、実績報告に写真を添付し成果を報告していただきたいと思います。
(赤石副会長)
それでは実績報告に写真を添付して提出するということを、事務局の方で確認していただいてよろしいでしょうか。
(事務局)
写真はこちらでも補助金の調査のときにとりに行くようにしています。
(角委員)
あと小学校などで苗から植えているところもありますが、経済面や子どもの情操教育的な面も考え、種から育ててみることも今後検討していただきたいと思います。
(赤石副会長)
市も花いっぱい運動は推進するということです。貴重な財源を使うということで、より効果的に活動を運営できる方法を地域振興課の方でも今一度考えていただきたく思います。
(事務局)
審査員からこのような意見が出たことを、決定通知に一言添えてお知らせしておきます。
(赤石副会長)
それでは京和自治会の申請を採択してもよろしいでしょうか。
<全員賛成>
(赤石副会長)
採択とさせていただきます。
続きましてあいあい境港はいかがでしょうか。
(三島委員)
コピーではなく印刷機を使ったら、もっと経費を節約できると思います。
(渡部委員)
今年は方針が変わったので、様々な面で模索しておられることと思います。内容についても昨年度の申請書は高圧的な書き方がしてありましたが、今回はやわらかい印象を受けました。
(石橋委員)
がんばって事業をしよう、続けようとする姿勢はかいたいです。
(赤石副会長)
補助金は1団体3年までということですが、この団体は補助金がないと継続は難しいと思います。今後どのようにして継続させていったらいいかアドバイスすることも必要です。
(事務局)
基本的には3年までですが、5年まで認められるケースもあります。でもその判断は難しいです。
(赤石副会長)
そのようなケースが出てからでは困るので、どんな時に5年まで認められるのかを事務局の方でも整理しておいていただけたらと思います。
それでは採択ということでよろしいでしょうか。
<全員賛成>
(赤石副会長)
採択とさせていただきます。
あと審査会のやり方についてですが、事前に11人集まって会を開き、代表3人が審査会に出席するというやり方はいかがでしょうか。
(事務局)
その場合、採択・不採択・修正の判断はどの段階でしますか。3人の審査員だけで結果を出しますか、それとももう一度11人で集まって結果を出すようにしますか。
(渡部委員)
結果はもう一度みんなで集まってするのがよいと思います。審査会の前に11人が集まり質問事項を決め、審査会後にもう一度11人で集まって結果を出すやり方はどうでしょうか。日にちをまたぐと負担も大きいので、1日で全て済ませるのががいいかと思います。
(事務局)
つまり1日のうちに、事前の会・審査会・事後(採択とするか)の会の3回の会を開くということですね。検討いたします。
(赤石副会長)
継続事業に関して。外江小学校への補助金はしらお会計の中に入っていると思うのですが、繰越金が43万円もあります。本当に補助金を交付する必要があるのでしょうか。
あと補助金6万円入ったことが決算書の中書かれていませんが、そのこともきちんと決算の中に明記する必要があると思います。
(事務局)
事務局側としても、繰越金が多い場合には補助金は出すべきではないという考えもあります。もし繰越金が年々増えるのであれば、補助金は出せません。しかしその繰越金はしらおの森ステージ修繕費用等の貯蓄ということも考えられます。決算書に関してですが、外江小の実績報告提出が今年度になってしまったため、まだ21年度補助金が支払われていない状態です。このため決算所の中に補助金6万円ということが挙がってこなかったのだと思われます。
(赤石副会長)
それならば、事業収支計画書の収入の中に21年度分の補助金が入ってないとおかしいと思います。少なくとも決算書、予算書のどこかに21年度分の補助金6万円は明記しておくべきだと思います。
(事務局)
そのことに関しては外江小学校にもう一度話を聞いた上で、指摘事項として、お伝えしたいと思います。
(赤石副会長)
上道小学校にも、補助金はどの会計に入るのか、実績収入内訳はどのようになったのか、聞いてみてください。
(渡部委員)
境港市障害児(者)育成会の緑化事業も決算書には出ていません。
(事務局)
この決算書は20年度分です。21年度の総会がまだなので、参考書類として20年度の決算書を提出していただきました。20年度は補助金を出しておりませんので、この決算書には載っていません。
(赤石副会長)
境港市障害児(者)育成会にも、決算書の中に補助対象事業に係る収支状況を明記していただき、事務局でしっかりと確認をするようにしていただきたいと思います。
<平成22年度 中海市長会事業計画について・続き>(別紙)
<閉会>
(別紙)
(別紙)
第3回境港市みんなでまちづくり推進会議会議録
~平成22年度 中海市長会事業計画について~
(事務局)
<説明>
(赤石副会長)
中海市長会事業について、何かありますでしょうか。
(角委員)
これらの事業は、住民の理解があった方がよりよい方向に進むと思います。事業のPRをうまくやっていただきたく思います。
(事務局)
中海市長会をPRするために中海圏域進行ビジョンのパンフレットを配布したり、ガイナーレ鳥取で中海市長会をPRしたりします。
(角委員)
いつ・どこで・どんなことがあるのかなど、もっと細かく住民に知らせてほしいと思います。
(事務局)
昨年度市報などでも市長会での事業を掲載しました。今年度も掲載したいと思います。ホームページにも事業に関することを掲載したのですが、そちらは見る人が少なかったようです。
(赤石副会長)
情報提供の場があるということだけでも、よいことだと思います。
未調整事業について。境港市には済生会病院がありますが、産婦人科がありません。近頃は皆さん米子の産婦人科に行っておられますが、やはり近くに産婦人科があった方が便利です。専門の先生に来ていただけるような医療面での連携を図ってもらえたらと思います。
(地域振興課長)
保健医療を担う病院への支援ということで、中海市長事業計画にあるような役割分担・連携をしていきます。また昨年度の例では、この事業で済生会病院に人工透析機を導入しました。米子市や松江市の病院にも必要な医療機を設置しました。そういった面で医療の連携は進めています。
(角委員)
高齢者が遠方の病院に行くのも大変です。交通手段や救急車の配置等も合わせて検討していただきたいと思います。
(石橋委員)
市報にふるさと納税が増えたと書いてありましたが、「ゲゲゲの女房」の効果ですか。それとも他にPRをされたのでしょうか。
(事務局)
「ゲゲゲの女房」の効果は大きいと思います。あとプレゼント商品の額が5000円にバージョンアップされたことも大きいと思います。
(赤石副委員長)
確定申告をしなければいけないのが面倒です。
(地域振興課長)
所得税・住民税のかかっている人は、控除となります。
サラリーマンの方に関しては年末調整後、確定申告の時期に寄附金控除をしなくてはなりません。しかし一般のサラリーマンの方でも医療費控除等で確定申告しているので、そのような方でも特別負担がかかるということはないと思います。
(赤石副会長)
他に何か話しておきたいことはありますか。
<特になし>
(赤石副会長)
それでは閉会にしたいと思います。