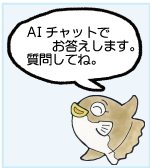第1回境港市みんなでまちづくり推進会議(平成22年1月21日開催)
第1回境港市みんなでまちづくり推進会議会議録
日時:平成22年1月21日(木)19:30~21:00
場所:市民活動センター
日 程
1.開会
2.委嘱状交付
3.市長あいさつ
4.各委員自己紹介等
5.会長、副会長の選出
6.説明事項
(1)今後のスケジュールについて
(2)中海市長会の事業実施状況・計画
(3)中海圏域の定住自立圏構想の進捗状況について
(4)第8次境港市総合計画の策定について
(5)市民アンケート調査結果について
7.市長との懇談
8.その他
9.閉会
□出席者(敬称略)
5.会長、副会長の選出
6.説明事項
(1)今後のスケジュールについて
(2)中海市長会の事業実施状況・計画
(3)中海圏域の定住自立圏構想の進捗状況について
(4)第8次境港市総合計画の策定について
(5)市民アンケート調査結果について
7.市長との懇談
8.その他
9.閉会
□出席者(敬称略)
赤石有平 石橋文夫 植田建造 柏木好輝
梶川恵美子 黒見久司 角 徹 土井哲雄
波田純子 三島智子 渡部敏樹
梶川恵美子 黒見久司 角 徹 土井哲雄
波田純子 三島智子 渡部敏樹
アドバイザー 関耕平
<開会>
<開会>
(事務局)
皆様、こんばんは。昨年の12月で「みんなでまちづくり推進会議委員」の2年間の委嘱期間が満了し、本日が新しく委嘱をお願いしてから第1回目の会議となります。では、市長からご挨拶をさせていただきます。
(中村市長)
皆様、こんばんは。本日は夜分にもかかわりませず、お集まりいただき、誠にありがとうございます。
皆様には、このたび「みんなでまちづくり推進会議の委員」をお願いしましたところ、快くお引き受けをいただき、重ねてお礼を申し上げます。
ほとんどの方には、再任していただいておりますが、今回からは、新しく植田建造様にも加わっていただきました。
また、島根大学法文学部の関先生におかれましても、引き続きご専門の立場からアドバイスをいただきたいと思っております。どうか皆様、引き続いてよろしくお願いいたします。
私は常々申し上げていることでございますが、これからのまちづくりには、「自分たちの住むまちは自分たちで考え、自分たちで創り上げていく」という意識や気風こそ大切であると考えており、これはまちづくりの基本でもありますし、自治の原点だと思っております。
協働への取り組みは、成果がなかなか目に見えないものですが、これからのまちづくりは、市民の皆様、市民団体の皆様、企業の皆様、私ども行政もそういった意識を持って、お互いに役割を分担しながら、対等な立場でまちづくりを進めていくことが重要だと考えております。
そして市政の柱のひとつとして「連携」を挙げております。これはどういうことかと申しますと、本市が有している重要港湾や国際空港といった極めて重要な社会基盤は、広範囲にわたる利活用があってこそ、その能力・機能が発揮されるものであり、地域の発展に寄与するものだと考えております。そういった観点から、より広い地域の皆様と「連携」をして大いに利活用していただくことが不可欠であると考えます。本市の周辺には松江があり、安来があり、東出雲があり、米子があるわけですが、それぞれのまちにいろいろな特性・基盤があります。お互いのまちが「連携」してそれらを利活用することによって、圏域全体の繁栄につながると考えております。
本市を含め、中海を取り巻く四市一町で構成する中海市長会というものがございます。これは、先ほど申し上げたことを共通認識として立ち上げられた組織でございます。これからこの圏域が将来どういった方向に向けて、手を携えて連携をしていくかという、ひとつの指針として「中海圏域振興ビジョン」づくりを手がけているところです。また、本市におきましても、まちの将来像や施策の方向性を定める「総合計画」の改定作業を進めているところであります。
そういった点について、この後、担当のほうから現在の状況、概要についてご説明をさせていただきますので、皆様には、どうか忌憚のないご意見をいただき、共によりよいまちづくりを進めていこうと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(事務局)
委嘱状の交付式につきましては、委嘱状をお手元に配布させていただいておりますので、省略をさせていただきたいと思います。
それでは、委員の皆様とアドバイザーの関様から自己紹介をご披露いただきたいと思います。
<委員、アドバイザー自己紹介>
(事務局)
それでは会議に入る前に会長、副会長の選出を行いたいと思います。事務局といたしましては、前回の会長の黒見委員、副会長の赤石委員に引き続きお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
<委員全員異議なし>
(黒見会長)
それでは日程の「6.説明事項」について事務局から説明をお願いします。
(事務局)
<説明、別添ファイル「資料1」、「資料2」、「資料3」、「第7次総合計画パンフレット」、「1月市報」参照>
(黒見会長)
今の説明内容について質問等がある方はいらっしゃいますか。
(赤石副会長)
「資料3」のP2の3で、「中海圏域の定住自立圏の形成に関する協定」がすでに締結したということが書いてあります。P3には「中海圏域振興ビジョン」と「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」はパブリックコメントを実施すると書いてあるのですが、協定を締結する前に協定を締結するかどうかについてパブリックコメントを実施してほしかったという思いがあります。
こういうことを中海圏でやっていこうということは私も大賛成ですし、協定を締結する期限があったのだと聞いておりますが、私たちにしてみますと、市独自で決定するものとパブリックコメントを実施するものとの棲み分けが分かりにくい部分があります。
(事務局)
今の赤石副会長のご意見はおっしゃるとおりだと思います。協定を作る際に、その内容についてパブリックコメントを求めるべきなのですが、国から示された協定の位置づけというものが、定住自立圏を作るためのものということでした。周辺自治体同士で協定を締結できる項目がたくさんあれば、それは定住自立圏であるという考え方であり、協定が締結できなければ、定住自立圏の圏域ではないという考え方です。
まず、中海4市は定住自立圏の先行実施団体となりましたけれども、定住自立圏をまず作ることをせよというのが国からの指導でした。定住自立圏を作ることはどういうことかというと、それは協定を締結することです。締結する案件が3分野ございまして、「資料3」のP2の表をご覧下さい。この3分野でそれぞれ最低1項目を設けなくてはなりませんでした。これが締結できれば国も定住自立圏と認め支援を受けられます。なかなか協定の案を皆様にお示しするまでの時間がなかったということもありますし、まず協定の内容が具体的なものではなく、その良し悪しを判断していただくには不十分であるので、国としてはこの協定をしっかり下支えするものを作るようにとのことでした。この下支えするものが「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」です。
「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」の中には、予算、事業計画など具体的に盛り込んであります。この「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」の素案が出来ましたら、パブリックコメントを実施しまして、皆様にご覧いただいてこれを補強するご意見をいただこうと考えております。
ですから、本来ですと、赤石副会長のおっしゃるように協定締結の際にパブリックコメントを実施するべきなのですが、「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」を皆様にご覧いただいた上で、「こういうことも連携できるのではないか」というようなご意見をいただければ、どんどん協定の項目が増えていきますし、定住自立圏が更に強固になるものと思います。それは私どもが求めていることでもあります。境港市の場合、協定項目が現在21項目あるのですが、これを重層的に増やしていこうというのが私どもの考え方です。
ほかにパブリックコメントを実施するのは、中海市長会の単独事業として予定していた「中海圏域振興ビジョン」です。これは「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」とは違い、中海圏域がどういう構想で連携していくのかを示すものです。
(赤石副会長)
ありがとうございました。私も中海圏域での連携をこれから密にしていくことは大事だと思っております。
(関アドバイザー)
先ほどのお話の中でひとつ確認をしておきたいのですが、例えばパブリックコメントで協定で想定していた範囲外の意見が出た場合は、協定にないからできないということではなく、より協定の内容を豊富化するというような考え方でよろしいのでしょうか。
(事務局)
そのような方向です。現在協定は21項目ありますので、この項目をどんどん増やしていくというイメージです。
(関アドバイザー)
それは、「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」のパブリックコメントの中で意見が出た場合に、協定に立ち戻って協定の中の項目を豊富化させるというイメージですか。
(事務局)
そうです。
(黒見会長)
ほかの方、何かありますでしょうか。
(渡部委員)
確認させてください。表題を掲げた段階で協定を締結して、その中身については協定の表題に基づいて議論をしながら付け加えていくということでよろしいですか。また「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」のパブリックコメントの中でその意見を求めていくということですね。
(事務局)
少し協定の内容を読み上げます。例えばいちばん最初の項目ですけれども、「生活機能の強化にかかる政策分野」の中で「医療」の項目がございます。「資料3」のP2の3の概要には「圏域にある救急医療、がん治療等を担う病院の診療昨日強化の支援」と書いてあります。読んでみるとなんとなく分かるような気がしますが、協定ですのでもっと具体的にしなくてはいけません。
協定には、まず「取組の内容」が書いてありますが、「医療機関の役割分担・連携により、適切な医療サービスが切れ目なく提供されるよう、保健医療を担う病院の診療機能強化について、必要な支援を行う。」とあります。
また「協定を締結した圏域の中心市の役割」としまして、「「松江市立病院」、「鳥取大学医学部附属病院」等の保健医療を担う病院の診療機能強化について、必要な支援を行う」とあります。
今度は「中心市以外の周辺市の役割」として、「保健医療を担う病院が行う診療機能強化について、中心市と連携を図り、必要な支援を行う。また、「鳥取県済生会境港総合病院」を始めとする医療機関が、行政区域を越えた近隣の中心市及び周辺市の住民に対し提供している医療機能についても、必要な支援を行う。」と書いてあります。これらが基本的に協定に盛り込まれています。
しかし、これだけだと病院の名前は出てきますが、具体的にどういう支援をしていくのかということが出てきませんので、それを「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」の中で示していこうという考えです。この「中海圏域定住自立圏共生ビジョン」で示したものをパブリックコメントで皆様からご意見をいただいてさらに補強していきたいと考えております。
(黒見会長)
ありがとうございました。ひとつ質問なのですが、市民アンケート調査の回収率の51.7%という数字について、市としてはどのように捉えていらっしゃいますか。
(事務局)
統計学上は、2000部配布した場合、150~300の回答があれば有意性があるとされています。
(中村市長)
なかなか難しいですが、7割くらいは回答をいただきたいところです。
(石橋委員)
関心のない方はあまり回答をされないのかもしれませんね。
(黒見会長)
それでは、「7.市長との懇談」に移りたいと思います。本日説明のあったことも含めて、その他境港市全般について忌憚のないご意見、質疑をお願いしたいと思います。
(石橋委員)
一昨年は観光客の入込数が172万人だったのに対して、昨年は157万人でした。新型インフルエンザ等の影響があり、この程度の減であれば良しとするかなと思いますが、「記録よりも記憶に残る境港市」にしていきたいと考えています。バリアフリー化等についてもお考えいただければと思います。
(中村市長)
昨年の観光客の入込数157万人は、この景気の低迷する中、新型インフルエンザの問題もありながら大健闘だと考えております。今、石橋委員がおっしゃられた「記憶に残る境港市」は本当にそのとおりだと思います。観光客の入込数の数字以外に、おもてなしの心がどの程度行き渡っているかということが「記憶に残る境港市」には大事だと考えています。
境港市は「魚と鬼太郎にあえるまち」ということで、魚と鬼太郎をミックスさせて情報発信をしているところですが、今の境港市は、魚を「獲る」→「食べる」で終わっています。
昨年夢みなとタワーで開催された「ニューカレドニアと南の島の水族館」にあったような、生きた魚に「触れる」、「楽しむ」というコンセプトが「魚と鬼太郎にあえるまち」には欠けているのではないかと思い、そこに何かもうひとつヒントがあるのではないかと考えました。今の状況を良しとしないで、バリアフリー化も含め、どういった取り組みでさらに魅力的な拡がりができるかを、「記憶に残る境港市」にするためにいろいろな方にご意見をいただきながら考えていく時期だと考えております。
(梶川委員)
今「記憶に残る境港市」というお話がありましたが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今年の2月に妖怪神社で結婚式を挙げる方がいらっしゃいます。大阪の方なのですが、いろいろなところを見て回られた上で、妖怪神社に決められたそうです。80人近く参列されるということで、すごく境港市のPRになると思います。
(中村市長)
水木しげるロードは、ハードを整備したのは行政ですが、ここまで賑わったのはいろいろな市民の方々の支えによるものだと考えております。大変ありがたいと思っております。
(石橋委員)
3月からNHKで境港市を舞台としたドラマ「ゲゲゲの女房」が始まりますので、観光客が増えてほしいという思いがあります。そのためには手をこまねいているのではなく、協働のまちづくりの一環として皆様で協力していきましょう。
(渡部委員)
せっかく172万人もの観光客が来ているのに、水木しげるロードだけ訪れて帰っている方が多いです。いろいろな思いを持った人も訪れていると思いますので、荒廃地となっている畑もたくさんありますから、そこに何か作ればそちらに回っていただけると思いますし、海の方に何か作ればそちらも回っていただけると思いますし、境港市をずっと回っていただけるようなものがあれば良いと思います。水族館があっても良いと思います。「境港市にはこんな所があった」、「境港市はすごい所だな」というような場所を作る必要があるのではないでしょうか。
今、私たちは夢の浜でさつまいもで焼酎を作っているのですが、東京で人気がありまして、注文に生産が追いつかない状況です。科学肥料も農薬も使わず畑で作物を作ってくれる人が増えれば生産を増やすことができます。第一次産業をもっと見直さなくてはいけないのではないでしょうか。第三次産業にばかり人が行くようではダメなのではないかと思います。農業であれ漁業であれ自然を満喫しながら取り組んでいけるものを作っていきたいと考えています。そういった境港市が作れたらと思います。
(黒見会長)
今、綿はどうですか。
(渡部委員)
綿も少し作っていますけど、販路が難しいです。
(中村市長)
昨年は市で1万平米作付けして、天候の加減で収穫はまだなのですが、専門の紡績会社では伯州綿の評価が非常に高いです。産業のレベルまで高められたらと考えています。最終的には収穫した綿で製品を作って販売したいと思っております。これで儲けようと考えているわけではなく、収支がゼロ、もしくは少々赤字でも荒廃農地がなくなっていけば大変良い事業ではないかと思います。
(黒見会長)
市民アンケート調査結果を読んでも、荒廃農地を活用してほしいという意見が多かったですからね。ひとつ雇用の拡大のためにもがんばっていただきたいと思います。
(渡部委員)
伯州綿は質はすごく良いのですが、糸にするのが難しく紡ぐ所が全国で2ヶ所しかありません。糸にできればエココットンとしてベビー用品としても需要があります。
(中村市長)
無農薬で赤ちゃん用のタオルを作って、医療機関に使っていただけたらと考えています。
(角委員)
私も雇用の面から考えても一次産業は非常に重要だと思います。境港市は食べる物も豊富、景色も良いわけですから、訪れた人を逃がさない方法をなんとか考えなくてはいけないと思います。先ほどお話がありましたが、境港市に水族館があればいいのにという意見はすごくよく聞きます。
(黒見会長)
昨年夢みなとタワーで開催された「ニューカレドニアと南の島の水族館」では、海の生き物に実際に触れるということが子どもたちには人気だったようですね。
(中村市長)
開催期間中の入場者は8万5千人でした。
(黒見会長)
それだけ魅力があるのですね。
(柏木委員)
今の子は自然を味わっていないと思います。自然に触れさせてあげるということが大切ではないでしょうか。
(三島委員)
昔は川や海で遊んでいましたからね。
(渡部委員)
命の循環も勉強できます。
(黒見会長)
波田委員は何かご意見がございますか。
(波田委員)
耐震改修は第二中学校のほかにどこをされるのですか。
(中村市長)
市内の小・中学校の耐震診断の結果、誠道小学校と第三中学校を除いて、耐震補強と大規模改造を行います。それと国の助成があるものですから太陽光発電の設備工事も行います。第二中学校については、いちばん古い建物なので全面的な建て替えを予定しています。
(波田委員)
少子化の問題からゆくゆくは第二中学校と第三中学校が合併するという噂を聞いたりします。いっそのこと中高一貫の公立の学校を作ってみてはいかがでしょうか。中学入試をしてみてはどうかと思います。また境港市には専門学校がないので、子どもが一旦は市外・県外に出て親元を離れてしまいます。そうすると仕送り等が大変なので、境港市にそういう学校があれば市外からも子どもが集まって良いのではないかと思います。
(柏木委員)
境港市の子どもは高校を卒業すると、毎年200人くらい県外に出ています。今まで一生懸命境港市で子育てをしたのに、県外に出てしまい帰って来るのはわずかです。市外から来てもらってなんとか境港市の人口が増えるようにしていただきたいと思います。
自治会は若い人が出て行ってしまって、高齢の方が多くなっています。自治会の区によっては子ども会が成り立たないところもあります。子どもが少ない区が合同で子ども会を作っているところもあります。これからは区の統合ということを考えていかなくてはいけないと思います。私は外江地区なのですが、ある区は360世帯あるのに対して、20数世帯しかない区もあります。区割りを見直さないとこれからの子どもたちは大変だと思います。
現在アパートがどんどん建っていますが、アパートに入居される方はなかなか自治会に加入されません。アパートの入居者を自治会に加入するようにしていかなくてはいけないと思います。
(中村市長)
その件については自治連合会でも話が出ています。
(事務局)
アパートの入居者が自治会に加入されないというのは、実は全国的な悩みであります。自治連合会でも一昨年、古いまちなかでがんばっている京都の自治会を視察に参りました。お話を伺いますと、自治会の考え方、役員の方の行動力、それが全てであるということでした。ひとつ驚いたのは、京都は女性の消防団員が多いということです。積極的に女性に参加を呼びかけているようです。
(柏木委員)
新しく境港市に転入していらっしゃった方が、本当に来て良かったと感じられるようにいかにあたたかく受け入れ、地区の行事に参加してもらうことが自治会の原点だと思います。
(土井委員)
自治会の区割りについて、私はいつも思うことがあります。中野西子ども会は80数人子どもがおり、中野東子ども会と合わせると100人近い人数になります。子ども会は自治会とは別のところで動いているので、今2つの子ども会では、区によって人数のバラつきがあるので子ども会の線引きを変えようかと話し合っています。ただ自治会があるので簡単にはいきません。
(柏木委員)
ただ子ども会も自治会から助成を受けているので、そのあたりが難しいですね。
(植田委員)
私は馬場崎町の自治会の副会長をしております。境港市の旧市内の現状なのですが、私の親戚が京町におりまして、京町は自治会が5つに分かれています。それぞれ合併したくないと考えているそうです。
(黒見会長)
誰かが手をつけなければいけませんね。
(植田委員)
自治会長さんが手をつけなければいけないと思います。
(中村市長)
地域のコミュニティですから、行政があれこれ口を出すのは難しいところです。地域の皆様がそういった意識を持って取り組んでいただければと思います。
(黒見会長)
どなたかほかに何かございますか。
(植田委員)
私は米子で環境学習を学校の先生と一緒に子どもたちに教えておりまして、ゴビウスに行ったり斐伊川水系を見たりして、直に魚や鳥や水に携わっています。ぜひ境港市でもこういうことができたら良いと思います。
もうひとつ、以前、ホテル誘致構想があったと思うのですが、将来的にどうなるのでしょうか。先ほど角委員がおっしゃられましたが、観光客に水木しげるロードだけでなく、いろいろ見て回っていただくために、宿泊施設があればいいのになと思います。
(中村市長)
ホテル誘致に関しては大苦戦をしております。継続的に話はしているのですがなかなか難しいです。
(渡部委員)
まず境港市に滞在できる環境を作ることが大切ですね。
(黒見会長)
では、赤石副会長、最後にご意見をお願いします。
(赤石副会長)
市議会の議員定数は今のままで良いのでしょうか。
(中村市長)
今、議員定数は16です。以前は24だったのですが、議会で16まで削減した経緯があります。これは人数が少なければよいのかというとそうではないと思います。やはり市民の代表の方ですから、たくさんいらっしゃればそれだけ市民の声を反映できると考えています。財政難から議員定数を削減しているのは全国的な流れなのですが、果たしてこれでいいのかという思いを私は持っています。境港市の議員定数16は、鳥取県の中でもいくつかの町の議員定数より少ないです。私はできればもう少し多くの人に市民の声を代弁していただければと思っております。ただ報酬の問題がございますので、これは議会の中で議論していただければと思います。現在議員報酬は自主的にカットされています。
(赤石副会長)
立候補者がもっとたくさん出てくるようになれば、境港市がもっと活性化すると思います。
(黒見会長)
昔はいろいろなことを議員さんに頼んで、それを市に言ってもらうような感じだったのですが、今は市民が直接市にお願いできるようになってきていますから、議員さんに頼む必要がなくなっているんですよね。
あともうひとつ、ここ30~40年、田後の船が境港を基地にしていて、8月31日に出港するときに寂しくぽつんぽつんと1艘ずつ出て行きます。今までの間、鉄工所や造船所等に対して多大な貢献をしていただいていますので、子どものブラスバンドでもよいのでなんとか賑やかに送り出していただくことを検討していただければと思います。
(中村市長)
田後には何度も寄ってお礼を言っておりますが、今黒見会長がおっしゃられたことは大切なことだと思います。
(黒見会長)
最後にアドバイザーから一言お願いいたします。
(関アドバイザー)
本日、私自身いちばん印象に残りましたのが自治会の問題でした。皆様ががんばっていらっしゃるNPOであるとかボランティアも重要ですが、一方で地域組織というのも同じくらい重要であると思います。NPO・ボランティア組織と地域組織の両方が元気になれば、より住民参加が実質化して前に進んでいくのではないでしょうか。実際に全国的な例を見ましても、両方が元気であるというところがキーになっています。自治会をいかに活性化していくかということは、今後も大きな論点として考えていく必要があると考えました。
(黒見会長)
ありがとうございました。それではこれにて閉会といたします。
<閉会>
別添
■資料1[pdf:43KB]■資料2[pdf:195KB]
■資料3[pdf:297KB]
■第7次総合計画パンフレット[pdf:1MB]
■1月市報[pdf:877KB]