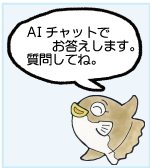第11回境港市協働のまちづくり推進懇話会(平成18年8月11日開催)
日時
平成18年8月11日(金) 午後8時30分~9時40分
(※会議開催に先がけ、同日午後7時から境港市青年会議所主催の講演会(会場:市民会館大会議室)において、中村市長が「協働」のまちづくりに関連した講演を行うとの情報を受け、急遽、座長提案により、出席委員の意向を確認したうえで、市長講演を傍聴した後に懇話会開催という日程となりました。)
(※会議開催に先がけ、同日午後7時から境港市青年会議所主催の講演会(会場:市民会館大会議室)において、中村市長が「協働」のまちづくりに関連した講演を行うとの情報を受け、急遽、座長提案により、出席委員の意向を確認したうえで、市長講演を傍聴した後に懇話会開催という日程となりました。)
場所
境港市市民活動センター
出席者(敬称略)
赤石有平 足立茂美 大西勝代 岡空晴夫 柏木好輝 高木春未 堀田收 渡部敏樹 湯越高志
(欠席委員:足立秋美 奥森隆夫 遠藤大輔)
アドバイザー:毎熊浩一 島根大学法文学部助教授
事務局:地域振興課長外2名
傍聴者:なし
(欠席委員:足立秋美 奥森隆夫 遠藤大輔)
アドバイザー:毎熊浩一 島根大学法文学部助教授
事務局:地域振興課長外2名
傍聴者:なし
日程
開会
あいさつ 赤石座長
検討内容
・(仮称)協働のまちづくり推進条例に関する素案骨子などの検討について
閉会
あいさつ 赤石座長
検討内容
・(仮称)協働のまちづくり推進条例に関する素案骨子などの検討について
閉会
会議の内容
【座長あいさつ】
【検討内容】
(座長)
今日は、今まで検討を行ってきた「(仮称)市民参加と協働を推進する条例案の骨子」検討結果のまとめと皆さんに事前配布した【みなさんの意見を募集します】と標題のある骨子概要を基に協議を進めたいと思います。
(事務局)…資料説明
資料1「(仮称)市民参加と協働を推進する条例案の骨子」資料の検討結果のまとめ」
資料2「【みなさんの意見を募集します】(仮称)みんなでまちづくり条例素案の骨子」
■資料1「(仮称)市民参加と協働を推進する条例案の骨子」資料の検討結果のまとめ[doc:58KB]
【検討内容】
(座長)
今日は、今まで検討を行ってきた「(仮称)市民参加と協働を推進する条例案の骨子」検討結果のまとめと皆さんに事前配布した【みなさんの意見を募集します】と標題のある骨子概要を基に協議を進めたいと思います。
(事務局)…資料説明
資料1「(仮称)市民参加と協働を推進する条例案の骨子」資料の検討結果のまとめ」
資料2「【みなさんの意見を募集します】(仮称)みんなでまちづくり条例素案の骨子」
■資料2【みなさんの意見を募集します】(仮称)みんなでまちづくり条例素案の骨子[doc:45KB]
(委員)
「議会の役割」を削る理由は。
(事務局)
資料1の8ページの吹き出しにあるように、議会も一市民の立場で関わっていく方向でよいかと。他の自治体についても、あまり事例がないようです。
この度の市報掲載においては、懇話会が「条例素案」の骨子を作成しました、という周知をして、併せて意見や感想を募集するものです。今回の市報掲載と出前説明会などで意見が出て、「議会の役割」もやはり必要との議論が高まれば、最終素案の条文に盛り込んで市長に報告することもありうるかと思います。
(毎熊アドバイザー)
資料1のままでは、市報に全部を掲載できないし、内容も難しく、また簡潔にしすぎても意見が出しにくいと思います。意見が出しやすいよう、もっとわかりやすく丁寧に作らなければならないと思います。
市報掲載の原稿案については本日の会で決定し、ホームページ、市内各所に備える詳細な解説は事務局と調整して、市報発行日までに作成するということではどうでしょう。
(委員)
条文のような(詳しい)ものを出すと、(市民の)皆さんはあまり見られないかと。原稿案のようにコンパクトにまとめてあると分かり易いと思います。
(地域振興課長)
市報掲載にあたっては、紙面スペースに限りがあり、骨子の柱だけについても全部掲載できないかもしれない。また、原案の表現の中に修正が必要な部分もあると思うので、委員の皆さんの意見をいただきたいと思います。
(事務局)
例えば、資料2のギリシャ数字の5.担保のところにある「市民一人一人の監視が・・・」というのは、具体的にはオンブズマン制度などの第三者機関がチェックするといった意味だと思いますが。
(委員)
それもありますが、市民が本気になって考えましょう、関心を持ってもらうということでもある。
(アドバイザー)
行政にはしっかりと条例(の適切な運用)を守ってもらいたいという意味で、こう表現したわけです。
(地域振興課長)
これから条例を作るのに、行政と市民が一緒にやっていくのだから、市民だけを主眼に置いた表現は避け、柔らかくした方がいいのではと思います。
(座長)
行政も市民も同じ立場で協力してやっていこうというのだから、「特に、・・・」とまで言わずに、片方を強調しなくてもいいとかと。
(委員)
市民と行政は責任の度合いも違うし、全く同じ立場でもないと思う。
(座長)
市民もこれからのまちづくりに責任を負わなくてはならないと考えます。官も民も。
(委員)
今回は主にどんなことについて意見を募集するのか。素案そのものなのか、考え方の部分なのか。
(地域振興課長)
今回は骨子、つまり骨組みについてのことです。市報の紙面の都合もありますが、それに注釈をどのように付けていくかです。
(委員)
意見募集の対象をどう捉えるか、委員間で統一した方がいい。
(座長)
この骨子は市報に掲載して、広く市民に知ってもらう、あとの項目ごとの詳しい部分については、公民館やインターネットで資料を見てもらうという形になるわけですよね。
(事務局)
市報に掲載しきれない各項目(参加、促進、支援など)の詳細な部分については、そのような方法になると思います。
パブリックコメントの実例として、まず「条文」の案を公表して、意見を募る、このやり方が結構多いです。また、宗像市のようにまず、骨子を掲載して、何か意見があればお寄せください、としている自治体もあります。
(一昨年の12月から、)懇話会が議論を重ねた結果、条例案の骨子ができましたので、策定の背景やこれまでの経過も踏まえて、市報で市民の皆さんにお知らせする、市報に載せきれない詳細は公民館、ホームページなどで閲覧できることなど、今回は周知をメインに実施し、寄せられた意見などを参考に条例素案の条文案を検討するということを考えています。
(委員)
いきなり条文案を(提示)、では市民の皆さんも分からないと思う。一度、骨子を公表したうえで、詳細資料の閲覧、あとは出前説明会などの方法を使って、周知をしていけばよいのでは。
(地域振興課長)
紙面構成はこれからの作業ですが、骨子の大枠については大方収まると思いますが。一部の箇所については校正が必要です。
(座長)
今までの話をまとめますが、とにかく「考え方」を(市民に)知ってもらうために市報に出すと、ただ、意見を出しやすい工夫もかなり必要に思う。
(アドバイザー)
今回はPRを主に、資料もできるだけわかり易く作成し、その際、意見を出してほしいポイントを明示する、例えば具体的に、「ボランティアの義務化」は必要ですか?などと問いかける感じではどうでしょう。
(委員)
連続シリーズものとして、何回かに分けて「参加」、「促進」とか項目ごとに、解説していくという方法もあると思います。
(事務局)
以前、市報で「協働」についてのコラムをシリーズ連載した例はありますが。月1回発行の市報で連載して、その都度意見を問うものにすると、12月までに(市長に素案を報告することが)間に合わないと思います。市報掲載などによる条文案のパブリックコメントを11月号に掲載するとすれば、10月中旬がリミットですし、日程がきついです。
(委員)
間に合うように日程を調整できないか。
(事務局)
以前お配りした進行表では、12月市報に最終案のパブリックコメントを募集となっており、委員の皆さんの任期が切れたあとに、寄せられた意見などの検討をすることになってしまいます。
(委員)
任期が切れても、ボランティアで(協議)すればよい。
(地域振興課長)
今から連載は時間的に無理なので、9月5日号は骨子などの概要を掲載し、市民に条例づくりへの関心をもってもらう。詳しい部分の解説は少し時間があるので、市報発行までに作成して閲覧してもらう。その後は出前説明会などの他の広報活動も実施しながら、11月以降に条文案の意見募集を行うという基本線でどうでしょう。
(委員)
11月に(意見募集を)して、12月に(最終案の)まとめをということでいいと思う。
(アドバイザー)
可能であれば、地元の新聞での連載で周知を図る方法も考えられますね。
(座長)
意見の出しやすい方法を考えるべき。
(委員)
本題の骨子概要資料の検討に入りましょう。
(アドバイザー)
条例名は、もっとわかりやすい名称がありませんか。(仮「みんなでまちづくり条例」以外に)
(委員)
私はこれで十分わかりやすいと思いますが。
(事務局)
単純に「まちづくり条例」とすると、全国各地では色々なタイプのものがあり、混同されることもあります。「みんなで」というところがポイントではと。
(委員)
みんなでまちづくり条例でいいと思います。(委員多数の意見)
(座長)
「担保」のところの表現はどうでしょう。
(事務局)
担保のところは、「第三者機関」と条例の見直し規定が主なものです。以前の懇話会でオンブズマン制度という話も出ましたが。
(委員)
「担保」という言葉がわかりにくいので、ほかにいい表現がないものか。
(委員)
カッコ書きの「実効性の確保」で大体わかるのでは。
(地域振興課長)
(行政に条例をしっかりと守らせる・・・という表現を)(市の責務にも含まれる)「職員一人一人の意識を向上させ、適切な運用を行う。」といったような感じで言い換えてはどうでしょう。
(委員)
職員一人一人の意識向上という表現はいいと思いますが、「行政」という集団は、やはり、力を持つものであると思いますね。(施策など)行政にやってもらいたいという意識も働きますし。
(座長)
行政は力が強いから、あえて原案の表現で、これからのまちづくりを変えていくんだ、ということと、そこまで強い表現でなくてもという意見が出ました。
(アドバイザー)
島根県に(条例案を)提案した時に、「改革」という項目を設けたのですが、最終的に削られました。最近になって行政が参加とか協働を盛んに言っていますが、財政的に厳しいなどの理由で市民に協働の名目で負担を押し付けているのではという疑念を少なからず市民は持っていると思います。私は一研究者として、行政がもっとしっかりと責任をもって、自らの襟を正し、参画とか協働を進めてほしいということで、島根県に「改革」という項目を提案したわけです。残念ながら、採用には至りませんでしたが。
簡単な表現方法としては、「みんなでまちづくりを進めるためには、行政も改革が必要です。」といった感じでもいいかもしれません。
(委員)
いいですね。行政も努力します、ということですから。
(委員)
行政も変わらなければいけない。
(委員)
行政も市民も一緒になって、協働のまちづくりを進める。行政もしっかりと改革していく。といった内容の表現で修正すればよいと思います。(その他の委員の意見も同じ内容。)
(座長)
では、この説明資料に市民の皆さんが質問や意見を出しやすいように、いくつかの項目について、ポイントの解説などを加えていただきたいと思います。
(委員)
みんなでまちづくり条例の愛称も市民から募集してはどうでしょうか。(そうですね。との声)
(事務局)
資料2の3ページのギリシャ数字2.参加の「2.具体的な取り組み内容」は、このような解説でよいですか。
(委員)
簡潔でわかりやすい表現であればよい。あまり長い説明は避けたほうがよい。(事務局で調整をお願いします。)
(座長)
次回の会議などの日程について、いつごろがよいか。
(事務局)
この後、条例素案の骨子概要が市報9月市報で掲載され、市民の意見などが出てくるのを待つとすれば、早くて9月の終わりから10月にかけて、になるかと思います。
(地域振興課長)
自治会の役員とか市民団体などに対しての「出前説明会」で意見を聴取する方法もある。
(委員)
(委員主体で、)出前説明会をやりましょう。
(座長)
その団体の会合時に併せて、(出前説明会の)開催を依頼すればどうだろう。
(地域振興課長)
9月中に実施できるように、自治会などの関係団体と日程調整をしてみます。
(委員)
事務局に調整をお願いする。
(座長)
では、出前説明会は事務局に調整をお願いし、必要に応じて研究会を開催ということにします。
「議会の役割」を削る理由は。
(事務局)
資料1の8ページの吹き出しにあるように、議会も一市民の立場で関わっていく方向でよいかと。他の自治体についても、あまり事例がないようです。
この度の市報掲載においては、懇話会が「条例素案」の骨子を作成しました、という周知をして、併せて意見や感想を募集するものです。今回の市報掲載と出前説明会などで意見が出て、「議会の役割」もやはり必要との議論が高まれば、最終素案の条文に盛り込んで市長に報告することもありうるかと思います。
(毎熊アドバイザー)
資料1のままでは、市報に全部を掲載できないし、内容も難しく、また簡潔にしすぎても意見が出しにくいと思います。意見が出しやすいよう、もっとわかりやすく丁寧に作らなければならないと思います。
市報掲載の原稿案については本日の会で決定し、ホームページ、市内各所に備える詳細な解説は事務局と調整して、市報発行日までに作成するということではどうでしょう。
(委員)
条文のような(詳しい)ものを出すと、(市民の)皆さんはあまり見られないかと。原稿案のようにコンパクトにまとめてあると分かり易いと思います。
(地域振興課長)
市報掲載にあたっては、紙面スペースに限りがあり、骨子の柱だけについても全部掲載できないかもしれない。また、原案の表現の中に修正が必要な部分もあると思うので、委員の皆さんの意見をいただきたいと思います。
(事務局)
例えば、資料2のギリシャ数字の5.担保のところにある「市民一人一人の監視が・・・」というのは、具体的にはオンブズマン制度などの第三者機関がチェックするといった意味だと思いますが。
(委員)
それもありますが、市民が本気になって考えましょう、関心を持ってもらうということでもある。
(アドバイザー)
行政にはしっかりと条例(の適切な運用)を守ってもらいたいという意味で、こう表現したわけです。
(地域振興課長)
これから条例を作るのに、行政と市民が一緒にやっていくのだから、市民だけを主眼に置いた表現は避け、柔らかくした方がいいのではと思います。
(座長)
行政も市民も同じ立場で協力してやっていこうというのだから、「特に、・・・」とまで言わずに、片方を強調しなくてもいいとかと。
(委員)
市民と行政は責任の度合いも違うし、全く同じ立場でもないと思う。
(座長)
市民もこれからのまちづくりに責任を負わなくてはならないと考えます。官も民も。
(委員)
今回は主にどんなことについて意見を募集するのか。素案そのものなのか、考え方の部分なのか。
(地域振興課長)
今回は骨子、つまり骨組みについてのことです。市報の紙面の都合もありますが、それに注釈をどのように付けていくかです。
(委員)
意見募集の対象をどう捉えるか、委員間で統一した方がいい。
(座長)
この骨子は市報に掲載して、広く市民に知ってもらう、あとの項目ごとの詳しい部分については、公民館やインターネットで資料を見てもらうという形になるわけですよね。
(事務局)
市報に掲載しきれない各項目(参加、促進、支援など)の詳細な部分については、そのような方法になると思います。
パブリックコメントの実例として、まず「条文」の案を公表して、意見を募る、このやり方が結構多いです。また、宗像市のようにまず、骨子を掲載して、何か意見があればお寄せください、としている自治体もあります。
(一昨年の12月から、)懇話会が議論を重ねた結果、条例案の骨子ができましたので、策定の背景やこれまでの経過も踏まえて、市報で市民の皆さんにお知らせする、市報に載せきれない詳細は公民館、ホームページなどで閲覧できることなど、今回は周知をメインに実施し、寄せられた意見などを参考に条例素案の条文案を検討するということを考えています。
(委員)
いきなり条文案を(提示)、では市民の皆さんも分からないと思う。一度、骨子を公表したうえで、詳細資料の閲覧、あとは出前説明会などの方法を使って、周知をしていけばよいのでは。
(地域振興課長)
紙面構成はこれからの作業ですが、骨子の大枠については大方収まると思いますが。一部の箇所については校正が必要です。
(座長)
今までの話をまとめますが、とにかく「考え方」を(市民に)知ってもらうために市報に出すと、ただ、意見を出しやすい工夫もかなり必要に思う。
(アドバイザー)
今回はPRを主に、資料もできるだけわかり易く作成し、その際、意見を出してほしいポイントを明示する、例えば具体的に、「ボランティアの義務化」は必要ですか?などと問いかける感じではどうでしょう。
(委員)
連続シリーズものとして、何回かに分けて「参加」、「促進」とか項目ごとに、解説していくという方法もあると思います。
(事務局)
以前、市報で「協働」についてのコラムをシリーズ連載した例はありますが。月1回発行の市報で連載して、その都度意見を問うものにすると、12月までに(市長に素案を報告することが)間に合わないと思います。市報掲載などによる条文案のパブリックコメントを11月号に掲載するとすれば、10月中旬がリミットですし、日程がきついです。
(委員)
間に合うように日程を調整できないか。
(事務局)
以前お配りした進行表では、12月市報に最終案のパブリックコメントを募集となっており、委員の皆さんの任期が切れたあとに、寄せられた意見などの検討をすることになってしまいます。
(委員)
任期が切れても、ボランティアで(協議)すればよい。
(地域振興課長)
今から連載は時間的に無理なので、9月5日号は骨子などの概要を掲載し、市民に条例づくりへの関心をもってもらう。詳しい部分の解説は少し時間があるので、市報発行までに作成して閲覧してもらう。その後は出前説明会などの他の広報活動も実施しながら、11月以降に条文案の意見募集を行うという基本線でどうでしょう。
(委員)
11月に(意見募集を)して、12月に(最終案の)まとめをということでいいと思う。
(アドバイザー)
可能であれば、地元の新聞での連載で周知を図る方法も考えられますね。
(座長)
意見の出しやすい方法を考えるべき。
(委員)
本題の骨子概要資料の検討に入りましょう。
(アドバイザー)
条例名は、もっとわかりやすい名称がありませんか。(仮「みんなでまちづくり条例」以外に)
(委員)
私はこれで十分わかりやすいと思いますが。
(事務局)
単純に「まちづくり条例」とすると、全国各地では色々なタイプのものがあり、混同されることもあります。「みんなで」というところがポイントではと。
(委員)
みんなでまちづくり条例でいいと思います。(委員多数の意見)
(座長)
「担保」のところの表現はどうでしょう。
(事務局)
担保のところは、「第三者機関」と条例の見直し規定が主なものです。以前の懇話会でオンブズマン制度という話も出ましたが。
(委員)
「担保」という言葉がわかりにくいので、ほかにいい表現がないものか。
(委員)
カッコ書きの「実効性の確保」で大体わかるのでは。
(地域振興課長)
(行政に条例をしっかりと守らせる・・・という表現を)(市の責務にも含まれる)「職員一人一人の意識を向上させ、適切な運用を行う。」といったような感じで言い換えてはどうでしょう。
(委員)
職員一人一人の意識向上という表現はいいと思いますが、「行政」という集団は、やはり、力を持つものであると思いますね。(施策など)行政にやってもらいたいという意識も働きますし。
(座長)
行政は力が強いから、あえて原案の表現で、これからのまちづくりを変えていくんだ、ということと、そこまで強い表現でなくてもという意見が出ました。
(アドバイザー)
島根県に(条例案を)提案した時に、「改革」という項目を設けたのですが、最終的に削られました。最近になって行政が参加とか協働を盛んに言っていますが、財政的に厳しいなどの理由で市民に協働の名目で負担を押し付けているのではという疑念を少なからず市民は持っていると思います。私は一研究者として、行政がもっとしっかりと責任をもって、自らの襟を正し、参画とか協働を進めてほしいということで、島根県に「改革」という項目を提案したわけです。残念ながら、採用には至りませんでしたが。
簡単な表現方法としては、「みんなでまちづくりを進めるためには、行政も改革が必要です。」といった感じでもいいかもしれません。
(委員)
いいですね。行政も努力します、ということですから。
(委員)
行政も変わらなければいけない。
(委員)
行政も市民も一緒になって、協働のまちづくりを進める。行政もしっかりと改革していく。といった内容の表現で修正すればよいと思います。(その他の委員の意見も同じ内容。)
(座長)
では、この説明資料に市民の皆さんが質問や意見を出しやすいように、いくつかの項目について、ポイントの解説などを加えていただきたいと思います。
(委員)
みんなでまちづくり条例の愛称も市民から募集してはどうでしょうか。(そうですね。との声)
(事務局)
資料2の3ページのギリシャ数字2.参加の「2.具体的な取り組み内容」は、このような解説でよいですか。
(委員)
簡潔でわかりやすい表現であればよい。あまり長い説明は避けたほうがよい。(事務局で調整をお願いします。)
(座長)
次回の会議などの日程について、いつごろがよいか。
(事務局)
この後、条例素案の骨子概要が市報9月市報で掲載され、市民の意見などが出てくるのを待つとすれば、早くて9月の終わりから10月にかけて、になるかと思います。
(地域振興課長)
自治会の役員とか市民団体などに対しての「出前説明会」で意見を聴取する方法もある。
(委員)
(委員主体で、)出前説明会をやりましょう。
(座長)
その団体の会合時に併せて、(出前説明会の)開催を依頼すればどうだろう。
(地域振興課長)
9月中に実施できるように、自治会などの関係団体と日程調整をしてみます。
(委員)
事務局に調整をお願いする。
(座長)
では、出前説明会は事務局に調整をお願いし、必要に応じて研究会を開催ということにします。