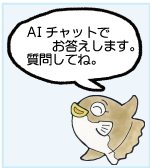令和7年8月定例記者会見(8月26日開催)
市長記者会見録
本日の記者会見は9月定例市議会提出議案についての1件となっております。
まず、報告案件が5件。「交通事故による損害賠償額の決定に関する報告」が2件と、「工事請負契約の変更に関する報告」が3件です。
議案は人事案件6件、予算議案2件、条例議案6件の計14件となっております。
人事案件の6件は、教育長、教育委員会委員および職員懲戒審査委員会委員の任命と、人権擁護委員候補者の推薦についてです。
次に予算議案は、一般会計と介護保険費特別会計の補正予算であります。
初めに一般会計の補正予算ですが、15事業のうち新規事業が3事業であります。補正額3億9133万9000円を増額して、補正後の予算額221億2492万8000円とするものであります。
補正予算の主な内容ですが、まず新規事業の「Jアラート受信機更新事業」であります。国が実施する全国瞬時警報システム(Jアラート)の更改に対応するため、同システムの受信機を更新するための経費385万円を増額します。
それと、新規事業の「米価・光熱費高騰に係る生活困窮世帯支援事業」であります。米をはじめ、電気・ガス料金を含む物価高騰が続く中、引き続き深刻な影響が懸念される生活保護受給世帯等の経済的負担を軽減するため、1世帯あたり8000円を給付するための経費524万2000円を増額します。支給対象世帯は、生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯など635世帯を予定しております。財源内訳は県2分の1、市2分の1です。
「老人福祉センターリニューアル事業」であります。来年度改修に向けて今年度は設計をいたします。この老人福祉センター別館を新たに建築するための実施設計費でありますが、この別館は市民のサークル活動での使用や、シルバー人材センターの作業場として利用することにしております。まずは令和8年度にはこの別館を建てて、それから老人福祉センターの改修工事をします。この改修工事中に老人福祉センターの代替施設として別館を使うという予定にしております。
次に、新規事業の「中身干拓地突発事故復旧事業補助金」であります。これは、中海干拓地内において、破損した土地改良施設の配水管の復旧工事を実施する米川土地改良区を支援する補助金53万3000円であります。
次に、「住宅・建築物耐震化促進事業補助金」であります。これは従来からやっていますが、近年市民の防災意識の向上もあり、また戸別訪問をするなど周知方法を充実したことにより、申請件数が当初見込みより増加したことに伴って、不足が見込まれる住宅の無料耐震診断に係る経費484万9000円を増額するものです。令和6年度は40件でありましたが、令和7年度は既に7月末で42件であります。29件分増えることを見込んで増額するものであります。その一方で、今年度に市内事業者が予定していた建築物除却の延期に伴い2864万円を減額するものです。
次に、介護保険費特別会計補正予算でありますが、これは「国県負担金補助金等返還金」として、過年度に交付を受けた国庫負担金等の精算に伴う返還金7780万4000円を増額して、補正後の予算額を41億4189万円とするものであります。以上が補正予算の内容であります。
次に、条例議案の6件について主なものを説明いたします。
議案第71号「境港市職員定数条例」の一部改正であります。現在の職員定数269人は維持しつつ、その内訳となる市長事務部局と教育委員会事務部局の職員定数を変更するものであります。市長事務部局の職員定数を232人から242人に10人増員する一方、教育委員会事務部局の職員定数を30人から20人に10人減ずるものです。これは職員の業務を勘案しての改正です。このほか、法令の改正などに伴い、所要の整備を行うものであります。
まず、報告案件が5件。「交通事故による損害賠償額の決定に関する報告」が2件と、「工事請負契約の変更に関する報告」が3件です。
議案は人事案件6件、予算議案2件、条例議案6件の計14件となっております。
人事案件の6件は、教育長、教育委員会委員および職員懲戒審査委員会委員の任命と、人権擁護委員候補者の推薦についてです。
次に予算議案は、一般会計と介護保険費特別会計の補正予算であります。
初めに一般会計の補正予算ですが、15事業のうち新規事業が3事業であります。補正額3億9133万9000円を増額して、補正後の予算額221億2492万8000円とするものであります。
補正予算の主な内容ですが、まず新規事業の「Jアラート受信機更新事業」であります。国が実施する全国瞬時警報システム(Jアラート)の更改に対応するため、同システムの受信機を更新するための経費385万円を増額します。
それと、新規事業の「米価・光熱費高騰に係る生活困窮世帯支援事業」であります。米をはじめ、電気・ガス料金を含む物価高騰が続く中、引き続き深刻な影響が懸念される生活保護受給世帯等の経済的負担を軽減するため、1世帯あたり8000円を給付するための経費524万2000円を増額します。支給対象世帯は、生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯など635世帯を予定しております。財源内訳は県2分の1、市2分の1です。
「老人福祉センターリニューアル事業」であります。来年度改修に向けて今年度は設計をいたします。この老人福祉センター別館を新たに建築するための実施設計費でありますが、この別館は市民のサークル活動での使用や、シルバー人材センターの作業場として利用することにしております。まずは令和8年度にはこの別館を建てて、それから老人福祉センターの改修工事をします。この改修工事中に老人福祉センターの代替施設として別館を使うという予定にしております。
次に、新規事業の「中身干拓地突発事故復旧事業補助金」であります。これは、中海干拓地内において、破損した土地改良施設の配水管の復旧工事を実施する米川土地改良区を支援する補助金53万3000円であります。
次に、「住宅・建築物耐震化促進事業補助金」であります。これは従来からやっていますが、近年市民の防災意識の向上もあり、また戸別訪問をするなど周知方法を充実したことにより、申請件数が当初見込みより増加したことに伴って、不足が見込まれる住宅の無料耐震診断に係る経費484万9000円を増額するものです。令和6年度は40件でありましたが、令和7年度は既に7月末で42件であります。29件分増えることを見込んで増額するものであります。その一方で、今年度に市内事業者が予定していた建築物除却の延期に伴い2864万円を減額するものです。
次に、介護保険費特別会計補正予算でありますが、これは「国県負担金補助金等返還金」として、過年度に交付を受けた国庫負担金等の精算に伴う返還金7780万4000円を増額して、補正後の予算額を41億4189万円とするものであります。以上が補正予算の内容であります。
次に、条例議案の6件について主なものを説明いたします。
議案第71号「境港市職員定数条例」の一部改正であります。現在の職員定数269人は維持しつつ、その内訳となる市長事務部局と教育委員会事務部局の職員定数を変更するものであります。市長事務部局の職員定数を232人から242人に10人増員する一方、教育委員会事務部局の職員定数を30人から20人に10人減ずるものです。これは職員の業務を勘案しての改正です。このほか、法令の改正などに伴い、所要の整備を行うものであります。
質疑応答
【記者】
報告第10号「議会の委任による専決処分の報告について(交通事故のよる損害賠償額の決定)」についてですが、人身事故ということで相手方の怪我の程度はどうでしょうか。
【産業部長】
横断歩道を渡っている歩行者に気づくのが遅れて事故になったということで、相手方は中学生で、打撲ということでした。被害者の方が警察に届け出をすると人身事故扱いになるということですが、届け出をされていなくて物損事故扱いになっております。ただ、今後どこかが痛くなるなどすると、人身事故扱いになる可能性もあると伺っておりますが、今のところ物損事故扱いとなっています。また運転手が減点や処分されることはないということを聞いておりますが、運転手が所属する会社の方もすぐさま研修や指導等をして運転手に対して注意喚起を行ったところでございます。
【記者】
老人福祉センターですが、別館の規模や全体のスケジュールを教えてください。
【福祉保健部長】
別館については、シルバー人材センターの作業ができるスペースというのを考えておりまして、最大100平米を予定しています。スケジュールについては、この9月議会で別館の設計費用を補正いたします。その後、令和8年4月もしくは3月から令和8年6月にかけて別館をまず建設工事をします。工事完了後、別館の方で今の老人福祉センターの事務室等として利用したり、もしくは百歳体操とかやっておられるようなグループに使ってもらったりしながら、令和8年7月から令和9年3月にかけて本館の改修工事をする予定です。
【市長】
今の建物がすごく老朽化していて非常に危ない状況ですので、シルバー人材センターの事務所も老人福祉センターに移転する予定です。
【記者】
イースタンドリーム号についてですが、昨年8月に就航してちょうど1年が経ちました。先般、船社の現地法人の方に伺いましたところ、年間で3317人の利用があったということでした。後は、輸入の方もパプリカを再開されたりとか、輸出の方も非常に活発で、コラーゲンだったりとかあるようです。あとは貨客ということで貨物の方も非常に大事かと思うところで、1航路100万円程度の補助金を出されていると思うのですが、1年の実績を市長としてどのように受け止めていらっしゃるかということと、今後の課題についてどういったものがあるかなど少しお話をいただいてよろしいでしょうか。
【市長】
乗客について1年間では3800人というような数字です。以前と比べれば非常に少ない印象を受けております。これは昔のDBSクルーズフェリーのときより運賃が高いということもありますし、韓国の旅行商品の運賃が高いので、乗船がそんなに多くないというところであります。それに伴って日本人もなかなか乗ってはいないという状況です。
また、貨物の方は韓国の物流が日本向けには釜山が一番太いという状況で、東海では地場産業もそんなに発達していないところもあるかもしれないですが、東海‐境港間は貨物量が非常に少ないという状況はいまだに続いている現状です。ですから、従来からあるパプリカとか、中古ボート、釣りの道具に加え、コラーゲンとか、養殖用の餌とか、量は少ないが新しいものが出てきていますけど、ベースカーゴがなかなか増えない状況ではあります。日本と韓国の輸出入において、どのような商品が良いのかをこれからもっと開拓をしていかないといけないと思います。イースタンドリーム号は、東海とウラジオストクを結んでおりまして、こちらは非常に乗客も貨物も好調であると聞いており、それによって航路を維持していると思っております。しかしながら、せっかく再開した海の道でありますので、しっかりと利用促進を図っていきたいと思っております。
また、毎年のように子どもたちのサッカー交流をしており、今年も8月初旬に東海のサッカーチームが来訪しました。去年は、イースタンドリーム号ではなく飛行機を使いましたけど、東海でサッカー交流をしています。このような子どもたちのスポーツ交流の際に、昔のDBSクルーズフェリーのときみたいに使ってもらえればと思っています。補助制度を設けていますので、しっかりとPRして民間交流を進めていきたいと思います。
また、フェリーに車を乗せて韓国から来訪し、車を使って日本を観光していただき、また車をフェリーに乗せて帰国するという商品もあります。多くの予約が入っており、現在30台ほどの予約が入っている状況です。従来は自転車をフェリーに積んでということでしたが、車を乗せて来訪できることで、より旅行の幅が広がると期待しております。
【記者】
外からのインバウンドも含めて、境港市の市政全般について、上半期終わったところでの感想や、後半に向けての取り組みを聞かせてください。
【市長】
まず、観光面では7月末で水木しげるロードの入込客数が100万人を突破したところですが、累計で言いますと対前年比90%程度しか昨年に比べて伸びていないところであります。関西万博などの影響で、関西の人が来なかったのかなというところもありますが、関西万博終了後の下半期は、鳥取県もしっかりとPRしていますので、こちらの方にお客さんが来ていただけたらと思っています。
水産業の方は、漁獲の水揚げ量は対前年比プラスで推移しています。ただ魚価・単価が低いため、水揚げ金額は対前年比91%程度となっています。その辺については心配をしていますが、9月からはベニズワイガニ、11月からは松葉ガニのシーズンが始まりますので、しっかりと産地境港をPRして、誘客も図る、商品の販売促進も図るということをやっていきたいと思っております。
また、水産振興ビジョンにおいて、改正されたビジョンで漁獲量水揚げ20万トンに対応する体制を作ると組み込まれています。漁獲量はマイワシやサバ類、マグロも資源量が上がっており、しっかりと生産はできています。それに対応する陸上の処理能力をしっかり水産業界一丸となって下半期取り組みたいと思っております。早速、水産庁長官と意見交換をする予定としておりますし、今後も水産業界と一緒になってしっかり体制を整え、準備をしていきたいと思っております。
報告第10号「議会の委任による専決処分の報告について(交通事故のよる損害賠償額の決定)」についてですが、人身事故ということで相手方の怪我の程度はどうでしょうか。
【産業部長】
横断歩道を渡っている歩行者に気づくのが遅れて事故になったということで、相手方は中学生で、打撲ということでした。被害者の方が警察に届け出をすると人身事故扱いになるということですが、届け出をされていなくて物損事故扱いになっております。ただ、今後どこかが痛くなるなどすると、人身事故扱いになる可能性もあると伺っておりますが、今のところ物損事故扱いとなっています。また運転手が減点や処分されることはないということを聞いておりますが、運転手が所属する会社の方もすぐさま研修や指導等をして運転手に対して注意喚起を行ったところでございます。
【記者】
老人福祉センターですが、別館の規模や全体のスケジュールを教えてください。
【福祉保健部長】
別館については、シルバー人材センターの作業ができるスペースというのを考えておりまして、最大100平米を予定しています。スケジュールについては、この9月議会で別館の設計費用を補正いたします。その後、令和8年4月もしくは3月から令和8年6月にかけて別館をまず建設工事をします。工事完了後、別館の方で今の老人福祉センターの事務室等として利用したり、もしくは百歳体操とかやっておられるようなグループに使ってもらったりしながら、令和8年7月から令和9年3月にかけて本館の改修工事をする予定です。
【市長】
今の建物がすごく老朽化していて非常に危ない状況ですので、シルバー人材センターの事務所も老人福祉センターに移転する予定です。
【記者】
イースタンドリーム号についてですが、昨年8月に就航してちょうど1年が経ちました。先般、船社の現地法人の方に伺いましたところ、年間で3317人の利用があったということでした。後は、輸入の方もパプリカを再開されたりとか、輸出の方も非常に活発で、コラーゲンだったりとかあるようです。あとは貨客ということで貨物の方も非常に大事かと思うところで、1航路100万円程度の補助金を出されていると思うのですが、1年の実績を市長としてどのように受け止めていらっしゃるかということと、今後の課題についてどういったものがあるかなど少しお話をいただいてよろしいでしょうか。
【市長】
乗客について1年間では3800人というような数字です。以前と比べれば非常に少ない印象を受けております。これは昔のDBSクルーズフェリーのときより運賃が高いということもありますし、韓国の旅行商品の運賃が高いので、乗船がそんなに多くないというところであります。それに伴って日本人もなかなか乗ってはいないという状況です。
また、貨物の方は韓国の物流が日本向けには釜山が一番太いという状況で、東海では地場産業もそんなに発達していないところもあるかもしれないですが、東海‐境港間は貨物量が非常に少ないという状況はいまだに続いている現状です。ですから、従来からあるパプリカとか、中古ボート、釣りの道具に加え、コラーゲンとか、養殖用の餌とか、量は少ないが新しいものが出てきていますけど、ベースカーゴがなかなか増えない状況ではあります。日本と韓国の輸出入において、どのような商品が良いのかをこれからもっと開拓をしていかないといけないと思います。イースタンドリーム号は、東海とウラジオストクを結んでおりまして、こちらは非常に乗客も貨物も好調であると聞いており、それによって航路を維持していると思っております。しかしながら、せっかく再開した海の道でありますので、しっかりと利用促進を図っていきたいと思っております。
また、毎年のように子どもたちのサッカー交流をしており、今年も8月初旬に東海のサッカーチームが来訪しました。去年は、イースタンドリーム号ではなく飛行機を使いましたけど、東海でサッカー交流をしています。このような子どもたちのスポーツ交流の際に、昔のDBSクルーズフェリーのときみたいに使ってもらえればと思っています。補助制度を設けていますので、しっかりとPRして民間交流を進めていきたいと思います。
また、フェリーに車を乗せて韓国から来訪し、車を使って日本を観光していただき、また車をフェリーに乗せて帰国するという商品もあります。多くの予約が入っており、現在30台ほどの予約が入っている状況です。従来は自転車をフェリーに積んでということでしたが、車を乗せて来訪できることで、より旅行の幅が広がると期待しております。
【記者】
外からのインバウンドも含めて、境港市の市政全般について、上半期終わったところでの感想や、後半に向けての取り組みを聞かせてください。
【市長】
まず、観光面では7月末で水木しげるロードの入込客数が100万人を突破したところですが、累計で言いますと対前年比90%程度しか昨年に比べて伸びていないところであります。関西万博などの影響で、関西の人が来なかったのかなというところもありますが、関西万博終了後の下半期は、鳥取県もしっかりとPRしていますので、こちらの方にお客さんが来ていただけたらと思っています。
水産業の方は、漁獲の水揚げ量は対前年比プラスで推移しています。ただ魚価・単価が低いため、水揚げ金額は対前年比91%程度となっています。その辺については心配をしていますが、9月からはベニズワイガニ、11月からは松葉ガニのシーズンが始まりますので、しっかりと産地境港をPRして、誘客も図る、商品の販売促進も図るということをやっていきたいと思っております。
また、水産振興ビジョンにおいて、改正されたビジョンで漁獲量水揚げ20万トンに対応する体制を作ると組み込まれています。漁獲量はマイワシやサバ類、マグロも資源量が上がっており、しっかりと生産はできています。それに対応する陸上の処理能力をしっかり水産業界一丸となって下半期取り組みたいと思っております。早速、水産庁長官と意見交換をする予定としておりますし、今後も水産業界と一緒になってしっかり体制を整え、準備をしていきたいと思っております。