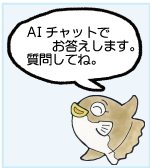第58回境港市都市計画審議会(平成21年9月4日開催)
第57回 境港市都市計画審議会会議録
議事日程
日 時 平成21年9月4日(金)午後1時30分
場 所 境港市役所 第1会議室
議事内容
議案第1号 鳥取県市街化区域と一体的な地域等にかかる開発許可等の基準に関する条例第3条の規定に基づく区域の指定について
審議会委員の出席者(12名)
会長 長栄 善二郎
会長代理 足立 收平
門脇 美保
荒井 秀行
松本 煕
永井 章
長谷川 具章 (境港管理組合港湾管理委員会事務局長)
竹内 悟 (境港水産事務所長)
長本 敏澄 (西部総合事務所県土整備局長)
宮本 京子 (西部総合事務所農林局長)
永井 忠志 (境港市連合自治会長)
薮内 明 (境港市農業委員会長)
薮内 明 (境港市農業委員会長)
(欠席者)
足立 統一郎
南條 可代子
藤原 博昭 (国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所長)
藤原 博昭 (国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所長)
説明のために出席した者
境港市建設部長 佐々木 篤志
都市整備課長 門脇 俊史
都市整備課主査 中垣 仁男
都市整備課係長 柏木 雅昭
都市整備課係長 柏木 雅昭
都市整備課主事 西 洋平
午後1:30開会
都市整備課長:
ただいまより、第58回境港市都市計画審議会を開会いたします。
本日の審議会は、委員15人中12人が出席されておりますので、審議会が成立していることを報告いたします。
それでは開会にあたりまして市長がご挨拶をいたします。
市長:
(挨拶)
都市整備課長:
市長は所用がございますので退席させていただきます。(市長退席)
引き続き、本日出席している事務局の紹介をさせていただきます。
都市整備課長:
(事務局紹介)
それでは会長、進行をお願いします。
会長:
お忙しい中ご出席ありがとうございました。審議会を進めたいと思いますが、その前に会議録署名委員は、荒井秀行委員、門脇美保委員にお願いいたします。
会長:
それでは議案第1号について事務局の方から説明をお願いします。
事務局:
(議案第1号について説明)
今回の案件に対してパブリックコメントを募集したところ、2件の意見がありました。1件目は「高松町の一部の区域が外れるのはなぜか。」という内容でした。これについては、区域の要件に該当しないので外しているわけですが、高松町と新屋町の町界付近で、区域界を明確にするために、一部区域を拡げることを検討している箇所があります。2件目は「説明会を開いてほしい」との意見でしたが、今回の区域指定は新たに義務を課すことや権利を制限するものではないこと、パブリックコメントで広く意見を求めていることから、説明会の開催を予定していません。
このパブリックコメントの意見や本審議会での意見を参考にして、区域を決定したいと思います。よろしくお願いします。
会長:
今回の審議会は、諮問を受けて答申をするものではなく、案に対して審議会としての意見を述べる場です。ただ今の事務局の説明についてご意見ご質問はございませんか。
委員:
今回の案件は、線引きの効力と等しいぐらいのイメージというふうに捉えてよいのか。
事務局:
いいえ、市街化区域と等しい土地利用をすることが目的ではなく、自己用住宅のない方が従来よりも簡単に家が建てられる区域を指定するということです。
委員:
今回の案件は、昭和46年の線引きに匹敵するくらいの画期的なものであると考えられ、もう少し時間をかけて議論すべきだと思います。現在の都市計画は、すでに町並みを形成している区域を市街化区域として位置づけ、後追い的な計画になっており、ここの地域をどうしたいのかという計画性が見えてきません。日頃から区域(線引き)を見直す必要があると感じていますが、見直しの審議をしてもらうために住民から提案ができるものですか。
幸朋苑の区画が、今回の指定区域から外れているのはなぜですか。半数以上建物がたっている区域に見えますが。
会長:
確認しておきたいのは、今回の案件は調整区域の中での話ですね。
事務局:
そうです。
委員:
県の審査会まで開かなくてよいということなのか。
事務局:
そうです。手続きは必要ですが、審査会に諮らなくても許可されます。
さきほどの荒井委員の意見についてですが、線引きについてはいろいろ議論があります。境港市、米子市、日吉津村の1つの都市計画区域の中で、人口に応じて市街化区域にできる面積が決まっており、簡単に市街化区域を拡大することは出来ません。なお、区域(線引き)の見直しについて住民から提起することについては、都市計画法の中に提案制度の規定があり、可能です。
また、幸朋苑の件ですが、医療施設であるとか社会福祉施設といったものについては、従来からある別の基準で許可を受けて建てることができます。今回は自己用住宅という用途を限定して区域を指定するものであり、幸朋苑の一画は当面自己用住宅が建つという見込みがないため外しております。将来の土地利用動向に応じて変更することも考えられます。
会長:
ピンクで着色している部分が今回指定する予定の区域ですね。
事務局:
そうです。調整区域の中でも農用地は指定できません。農用地を除く調整区域の中で、一団の土地に住宅用敷地が半分以上を占める区域を指定しています。今回の指定から外れた場所でも、分家人などの別で定める基準に適合すれば、家を建てることができます。今回の指定に入っていない一団の土地に分家住宅などが徐々に建ってきて、基準を満たすようになれば、区域に含めることができます。
会長:
ピンクの指定区域では、自己用住宅を建てる際に、手続きが簡便になったということですね。今回求めている意見は、区域の要件や建てられる建物についての意見ではなく、区域の範囲についての意見ですね。
事務局:
そうです。今回の案については、できるだけ広く区域をとっております。
委員:
一団の区域の捉え方はいろいろあると思うが、この指定区域は大きな一団の区域として捉えて定めたものなのか、小さな一団の区域で判定してそれを積み上げていったものなのか、どの程度の一団の区域で考えたのか、その作業の過程を教えてください。
事務局:
最初は最小の範囲で適合するかを判断し、それらを積み上げる作業をしましたが、まばらになるという不都合が生じるため、主要な道路などで囲まれたある程度広い範囲で適合するかを判断し、積み上げをすることとしました。さらに、積み上げをした指定区域の境界沿い(外周部)については、再度最小の範囲を捉えて、除外すべきか含めるべきか精査した結果、このような区域となりました。
委員:
ということは、一団の土地の捉え方については、市に裁量権があるということで、県の開発審査会でのポイントは、その考え方や作業の過程になると思います。また、このような区域を指定する場合には、わかりやすさが重要となり、抜けが生じたり、まばらであったりするより、大きな範囲で捉えて住民にも分かりやすい区域であればいいと思います。その辺の過程については、皆さんに説明をしておくべきものだと思います。
会長:
調整区域の中で厳しい制限を緩和するという流れであるならば、あまり小さなことを考えず、多少裁量を活かして、住民にわかりやすい形にするために、境界のくぼんだ部分をまっすぐにすることもいいのではないのでしょうか。
委員:
西森岡の一部が指定区域から外れているのはなぜか。住宅も建っているように思えるのだが。
事務局:
西森岡については、大きな道路で囲まれる範囲を考えた場合、住宅用敷地の占める割合が半分以下となり、指定区域に入りません。部分的に住宅が密集している箇所を区切るような道路でもあれば、その箇所を区域に入れることができるのですが、そのような道路がないため、指定区域から外しています。
委員:
何年後かに区域を見直すということは決まっているのか。また来年にでも区域に入れてくれという要望があれば入れられるのか。
事務局:
見直しの時期は決まっていません。また、要望を受けて見直しをするのではなく、土地利用動向に応じて要件に該当するような箇所がでてくれば、区域に入れていきます。
委員:
東森岡と西森岡地区が全て指定区域に入ればいいなと個人的に思っていたが、説明を受けてわかりました。同じ町内で差があるということに対して住民の方が納得されるのかなと疑問です。
会長:
自己用住宅が建てられるということですが、調整区域の固定資産税はどのようになりますか。
事務局:
現在、市街化区域と調整区域の農地の固定資産税については大きな開きがあります。今回の指定区域に入ったからといって、調整区域の評価の仕方を変える予定はありません。自己用住宅が建つということで多少全体的に評価が上がる可能性はありますが、急激に上昇するということはないと思われます。
委員:
下水道で三軒屋町の通信場付近の一部分が、下水道の認可区域から漏れていたことがあった。そういったことはないのか。
事務局:
そういったことはありません。
委員:
このように規制が緩和されることで申請がしやすくなり、市外からの人口増につながるのではないか。夕日ヶ丘の件もあるが。
会長:
調整区域の土地を買って建てる場合、どのような手続きが必要ですか。また、調整区域に既に家を持っている人が、別の調整区域の道路の広いところに家を建てることはできるのですか。
事務局:
家を建てる土地が農地であれば、農地転用の申請と開発行為の申請が必要です。また、市街化区域に土地を持っている人は建てることができませんが、調整区域に土地を持っている人が、別の調整区域の便利のいい土地を求めて建てることは可能です。すでに家を持っている人が建てる場合には、既存の家が無くなる(取り壊す)というような証明が必要になります。
委員:
農用地は従来どおり規制がかかっており、今回のことでの乱開発にはつながらないので、都市計画上は問題ないと思います。また、米子市において、道路要件に2項道路が入っていないが、境港市は2項道路でもいいのですね。
事務局:
そうです。当市で米子市のように考えますと、指定する区域が限られてしまいます。ただし、米子市の場合は既存宅地については従来どおり認められています。
委員:
農業振興担当とも協議しましたが、問題はないとのことでした。ちょっと心配なのが、枕川の改修事業を行っておりまして一部区域に入っています。枕川は農業を目的とした川ですので家が建て込んでくると川の汚染等につながらないよう協力していただきたい。
事務局:
わかりました。協力していきます。
委員:
JR境線沿いの区域で、農地としては利用できない、宅地にする以外は使い道がないような区域があります。土地の有効利用という観点から、これらの地域を宅地化していくという線引きの見直しが必要だろうなと感じています。後追いではなく、将来のまちを誘導するような都市計画としていただきたい。
会長:
線引きの見直しなどの根本的な議論については、議会などの別の場で議論が必要であると思います。
委員:
自己用住宅のみが対象なのでしょうか。
事務局:
そうです。ただし、自己用住宅には店舗兼用住宅を含みます。
事務局:
先ほどまでの議論を聞いておりますと、高松町のくぼんだ部分と西森岡の部分をどのように扱うのかというご意見が多かったように思います。このことを市長に報告して判断していき
たいと思います。
会長:
他にありませんか。
この審議会での意見がそのまま採用されるわけではありませんが、意見を報告していただき、市長が判断する際の参考にしていただければと思います。
それでは、これをもって第58回境港市都市計画審議会を終了させていただきます。本日は長い間ありがとうございました。
午後2:30閉会
お問合せ先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市建設部都市整備課
電 話 0859-47-1066
F A X 0859-44-3001
E-mail toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市建設部都市整備課
電 話 0859-47-1066
F A X 0859-44-3001
E-mail toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp